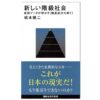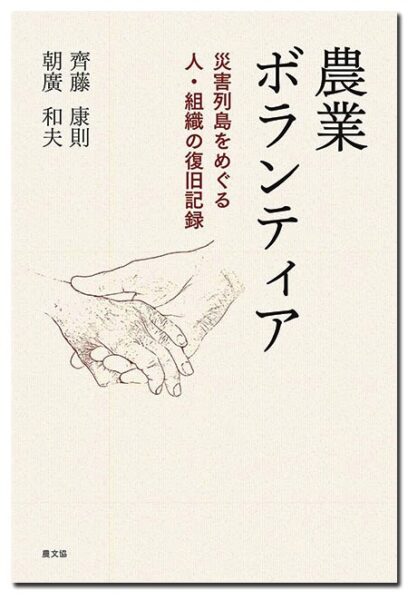 毎年のように日本列島のどこかを襲う自然災害。国は被災地を放置し、地方の田舎である被災現場は少子高齢化で助け合いもままならない。そんなときに頼りにされるのがボランティアだが、社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターがおこなうのは、住居の泥出しや片付け、ゴミ搬出、炊き出しや物資支援といった生活支援に限られる。取り残されるのは農地や農業施設の復旧だ。
毎年のように日本列島のどこかを襲う自然災害。国は被災地を放置し、地方の田舎である被災現場は少子高齢化で助け合いもままならない。そんなときに頼りにされるのがボランティアだが、社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターがおこなうのは、住居の泥出しや片付け、ゴミ搬出、炊き出しや物資支援といった生活支援に限られる。取り残されるのは農地や農業施設の復旧だ。
農業は農家の生計手段であり、農地の復旧が遅れ未収穫期間が長くなれば、生活再建はきわめて困難となる。永年性作物である果樹などは、根が泥に埋まったままだと呼吸できなくなり、木が枯れてしまうこともある。なかには「被災したから」「高齢だから」という理由で、それを機に農業をやめる農家も少なくない。
そうした農家の窮状を受けて、東日本大震災の頃から各地のボランティアやNPOによる下からの自発的な試行錯誤を経て立ち上げられたのが「農業ボランティア」だ。もちろんまだ定まった主体や機関はなく、制度的な根拠もないが、現地の農家とボランティアやNPO、JAや行政との相互関係のなかで発展してきている。
そして農業ボランティアがやる復旧作業とは、①用水路の土砂の除去、②田畑の石拾いや土砂出し、③ビニールハウス流出後の片付け、④果樹の根元の土砂出し、⑤石垣の復旧、⑥作付けや稲刈り(瓦礫が散乱し機械が使えない場合など)、⑦草刈りや共用施設の管理、⑧販売支援、などだ。
この本の目的は、2010年代に発生した災害に対して展開されてきた農業ボランティアのとりくみを、緑地保全学と地域社会学を専攻する2人の研究者が具体的に描き上げることだ。東日本大震災(2011年)の被災地である宮城県仙台市、九州北部豪雨(2012年)の福岡県八女市・うきは市、熊本地震(2016年)の熊本県西原村、九州北部豪雨(2017年)の福岡県朝倉市、西日本豪雨(2018年)の愛媛県宇和島市、東日本台風(2019年)の長野県長野市――の事例が紹介されている。
仙台圏の学生で立上げ 農家と思い共有し
ここではそのなかから、宮城県仙台市のとりくみに注目してみた。
「東北地方の穀倉地帯」の一つである仙台東部地域には2300㌶の農地が広がっているが、東日本大震災の大津波によってその八割、1800㌶が被災した。仙台市内の被災農家は941戸を数え、死者・行方不明者930人には100人をこえる農業関係者が含まれていた。市内の農地、農業用機械・施設、土地改良施設などの被害総額は721億円と推計された。
一方、国はこの地域で「競争力の高い大規模生産・大規模販売型の農業」を進めてきた。宮城県の復興計画でも、民間資金の活用や企業の農業算入によるアグリビジネスの推進ばかりが強調され、小規模・零細農家は放置されていた。生活支援に限られる災害ボラセンは、農地の瓦礫撤去や倉庫・作業場の泥かきは、農家の経済活動に直結するため手を出せず、被災した田畑は手つかずのまま残された。
このとき、「復旧から復興へ、そして地域おこしへ」を合言葉に、仙台圏の大学生たちによって構成される震災復興・地域支援サークル「ReRoots」が立ち上がった。
メンバーは、若林区の農業生産者グループに話を聞いた。
大きな瓦礫はブルドーザーやショベルカーですでに撤去してあった。しかし畑の中には金属の棒や石、ガラス片、プラスチックなどが無数に埋まっており、歯を傷めるのでトラクターを入れられないし、手で苗を植えると怪我してしまう。こうして週末、大型バスで駆け付けた100人規模のボランティアが畑に横一列に並び、日が暮れるまで土の中から瓦礫を拾い上げていく作業を続けた。被災した畑の7~8割から瓦礫を取り除いたという。
メンバーは次には、農家一軒一軒の聞きとりをおこなった。依頼を受けた作業だけをやるのでなく、農家の人となりや家族の話、どうやって逃げたか、この畑でなにをつくってきたか、どう再建したいかを理解するためだ。話を聞くうちに、農家の技術の高さや仕事への誇り、「こんな被災があっても俺たちは負けない」などの気持ちに触れ、その生き方に引き寄せられたという。
自ら耕し、行事を支え 就農するOBも
メンバーは2011年の秋、耕作放棄地で野菜を作り始めた。「ボランティアをする側とされる側の距離感、外から入っているという関係を突き破りたかった。真似事かもしれないけど、僕たちも農業をやって、この地域を復興させたいと思うようになった。農家の悩みに寄り添い、それを共有できなければ、復興をめざすなどとはいえない」
営農が一部再開された翌年の秋、メンバーは仙台朝市の一角に「若林区復興支援ショップりるまぁと」をオープンし、農家の販売を支援した。
一方、震災復興計画による上からの大規模化・法人化のなかで、若林区内には14の農業法人ができた。しかし農業者の平均年齢は60代後半で、後継者は乏しく、10年後どうなるかは未知数だ。人口は大きく減少し、個人営農は離農が続き、町内会の運動会もお祭りも維持できないという、コミュニティ存亡の危機に直面していた。
そこでメンバーは、「まちづくり部会」など地元主導型のワークショップに参加し、夏祭りや運動会など地域行事の後方支援に着手した。また、「地産地消の推進と買い物難民の解消」を掲げて移動販売を始め、元の住民たちのいる災害公営住宅団地に野菜を届けて、「食のサロン」も開催。さらに果樹づくりやおいもプロジェクト(さつまいもの栽培・収穫)を通じて、都市住民と被災農家の新たな交流機会をつくり出していった。
こうしたなかで、メンバーのOB・OGの中から地元に残って就農する新規就農者が次々に出た。2020年に設立した「仙台あぐりる農園」は、学生時代にメンバーだった20代の女性が代表を務める農業法人で、クラウドファンディングで農業機械を購入し、約50㌃の農地でサニーレタス、トウモロコシ、ブロッコリーなどをつくり、地元スーパーの産直コーナーに出荷している。「農業の担い手であり地域の担い手」となる若手人材を育成するために、「農村塾」もスタートさせた。
こうしたとりくみには、中心メンバーの「ボランティアは復旧・復興の主体ではなく、被災者の主体性を引き出す媒介だ」という強い問題意識があるようだ。それはかつて参加した反原発運動の浮き草のような運動を克服し、その土地に根ざした復興を支えるとりくみをしたいという自分自身の反省からきている。
これは一例だが、この本を読むと、災害列島に広がる農業ボランティアは、都市住民と農村住民が連携した「農ある暮らし」――新しい市民社会形成の一つの契機になるのではないかと思わせるものがある。
(農山漁村文化協会発行、四六判・352ページ、定価1800円+税)