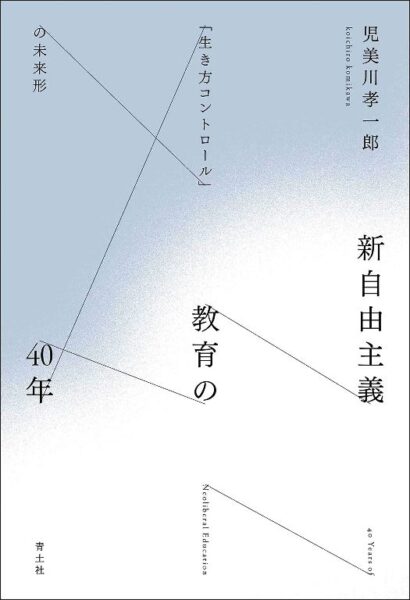 小学生同士のケンカなのに、そこに親が口を出し、教師の指導が悪いといいはって聞かない。そうした親はごく少数なのだが、声が大きいだけに学校が対応に苦慮し、なかにはそれを契機に病気になったり、退職したりする教師が出る。「戦後の画一的教育を改める」といい「教育の自由化」「個性重視」が叫ばれて40年、その間にはマスメディアによる「体罰」・教師バッシングもあり、教師は萎縮し、その指導性は否定されてきた。そしてその教育で育った子どもが大人になり、人間関係をめぐる様々なトラブルが伝えられている。
小学生同士のケンカなのに、そこに親が口を出し、教師の指導が悪いといいはって聞かない。そうした親はごく少数なのだが、声が大きいだけに学校が対応に苦慮し、なかにはそれを契機に病気になったり、退職したりする教師が出る。「戦後の画一的教育を改める」といい「教育の自由化」「個性重視」が叫ばれて40年、その間にはマスメディアによる「体罰」・教師バッシングもあり、教師は萎縮し、その指導性は否定されてきた。そしてその教育で育った子どもが大人になり、人間関係をめぐる様々なトラブルが伝えられている。
著者は、教育哲学を学んでいた学生時代、中曽根内閣の臨教審が「教育の自由化」をうち出したことに直面。それを疑問に思い、以来「新自由主義教育改革」について問題提起をおこなってきた。この本は、新自由主義教育改革の40年を振り返るとともに、その教育改革が現在、これまでの日本の教育が経験したことのない地平をこじ開けようとしていると警鐘を鳴らしている。
Society50とは 経団連が提唱
著者によれば、新たな教育改革は、中西宏明・日立製作所会長(後に日本経団連会長)が提唱した未来構想「Society5.0」を、当時の安倍政権が国家戦略にした2016年以降、顕著な形をとってきたという。従来のように文科省や中教審が発信源ではなく、首相官邸や内閣府のお墨付きを得た経産省が主導するものになっていることが特徴だ。Society5.0の国家戦略化を契機に、経産省が教育政策遂行の前面に乗り出し、補助金を駆使した実証事業などを全面的に展開し始めた。
Society5.0とはなにか? それは、人類社会の発展を狩猟社会→農耕社会→工業社会→情報社会ととらえ、これに続く新たな社会(=5.0)を「最新テクノロジーの発展に支えられて、サイバー空間と現実空間が高度に融合し、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」(内閣府)としている。いいことづくめの眉唾ものだが、社会の隅々にICT(情報通信技術)やAI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ビッグデータ、ロボット工学等の最新テクノロジーを張り巡らした「超スマート社会」をつくろうとしているようだ。
それをめざして経産省が、教育産業起点のイノベーションを学校にも広げていくという方向をうち出している。戦後の教育では、公教育と塾や予備校などの教育産業とは「棲み分け」「相互不可侵」の関係だった。ところが新たな国家戦略のもとではその垣根がとっ払われ、公教育の民営化、市場化を一気に進めようとしている。
しかもそこでいう教育産業とは、塾や予備校だけでなく、IT業界や人材ビジネス、コンサル業界までを含む壮大なもので、すでに教育内容や教育方法、評価、教育の担い手などの「開発」を始めている。公教育の提供主体が民間に開放され、民間企業が公教育のあらゆる分野を波状的に改変していく危険性があるという。
経産省の具体的イメージはこうだ。すでに開発に着手している「AIドリルによる個別最適化された学習の実現」を見てみよう。AIドリルは学習が個別化されるので、そもそも教室で学ぶことを必要としない。学年、クラス、標準授業時数も必要なくなる。教師さえも必要なく、子どもたちは一人一台端末を前に個別に学習することになる。意欲がなくなり学習に集中できなくなった子は「自己責任」と認定される、学力格差はこれまで以上に開き、不登校も増えるだろう。
これまでも文科省の教育改革は産業界の意図を意識したが、経産省の構想はより露骨に産業界の人材要求を意識し、それをスリム化した学校(経産省の構想では、運動会や修学旅行などの行事や、クラブ活動、生徒会活動などの特別活動は存在しない!)によって達成しようとしている。学校教育の解体であり、人間的な成長の機会を奪う愚かな試みというほかない。
そして、コロナ禍というショックを利用し、「GIGAスクール構想」によって子どもたち一人一台の端末を配り、学校のネットワーク環境を整備したのも、こうしたSociety50型教育の土台づくりだったと著者は指摘している。
焦土から築いた義務教育 教育の営み否定
80年前に戦争が終わり、焦土の中から先人たちは日本の復興に勤しみ、次代の担い手を育てる教育は機会均等をめざさなければならないとたたかった。義務教育無償はその第一歩で、せめて義務教育だけは国の負担で、貧富にかかわりなく平等に受けさせることを求めたのだ。それは国の文化を高め、経済を繁栄させていくうえでも重要なことだった。そして教師は、子どもたちへの愛情を根底に、子どもたちの家庭環境や性情を知り抜き、彼らを集団のなかで知育・徳育・体育の全面で成長させることを誇りとしてきた。
それが今、政府・経産省は公教育の原則を否定し、子どもを育てる教育の営みも否定しようとしている。運動会も修学旅行も部活もなくなり、一つの目標に向かってみんなで頑張ったり、運動が苦手な子ができるようになったことをクラス全体が喜ぶような、そんな感動がなくなったら、誰もそんな場所(もはや学校ですらない)には寄りつかなくなるだろう。
この本のなかでもう一つ注目したのは、著者が新自由主義教育を批判する側の課題を指摘している点だ。「威勢はいいかもしれないが、平板な紋切り型の批判を投げつけているだけでは、かえってわれわれの思想的営為を貧しくしてしまうだけ」であり、新自由主義を受け入れてしまう側の弱点にも目を向けなければならない、と。
著者がとくに注意を促すのは「新自由主義リベラル」とでも呼ぶべき社会意識である。既存の公教育(学校教育)の閉鎖性や硬直性、集団主義に批判的であり、民間の教育にそうした弊害のない場所を期待する意識だ。経産省が推奨する新教育産業には、多様性や個性重視という理念を前面に押し出す「事業型NPO」や「社会的企業」も少なくないそうだ。
かつて「教育の自由化」「個性重視」が持ち出されたとき、教育者としての使命を放棄し勤務時間などの待遇改善にのみ運動を切り縮めてきた日本教職員組合中央が、文科省のパートナーとなってそれを推進したことが思い起こされる。日本の次代の担い手としてどんな子どもを育てるのか、という教育論議を活発にすることが求められているのではないか。
(青土社発行、四六判・342㌻、定価2800円+税)
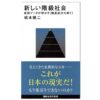





















昭和40年前後であったと思うが,「期待される人間像」といった言葉が経済界から発せられた。教育が企業戦士あるいは富国のための労働者を育成する役割を主に担わされた時代があった。最近の予算編成でも経済産業省が省をまたいで予算を組んでいる。つまり文科省は経団連の配下にあり,経産省の駒の一つであってきたのであろう。しかもそれもやむを得ない。英文学者故中野好夫氏の話を聞くまでもなく,文部省役人は5流、6流の役人であるそうな。
現在,前川喜平氏が「三ジジ放談」で国民に人気があるが,森友学園の設立を認めた大阪府の私学設置委員会の委員長は文科省インナーの梶田叡一氏で,設置条件を満たしていないのに条件が近いうちに揃うので設置を認めてはどうかとまとめあげた人物である。安部昭惠・谷系列,財務省・国交省に関連した文書改竄系列の一角である梶田は,大学長を6つ、7つも務めた御仁である。教育が良くなるわけがない。
また外国人留学生を大量に受け入れている今治の加計学園の分校△も設置条件を悪用した結果出来上がった。BML4つまり細菌研究所などが今治の研究にはうってつけのようだが,八王子だ,長崎大学だと騒動が起きている。認知症がかなり進んでいるので正確ではないが,文部官僚が教育をダメにしている。
新自由主義を教育に持ち込むなと主張されたのは教育学の藤田教授。アメリカでは成功しなかった教育,ビル・ゲイツなどが主張する教育改革が成功するわけがない。文科省はやるに事欠いて英語を小学校に導入した。Crazyぐらいしか口から出せなかった中学生たちを思い出すが,最近では「私は美しい」とあいさつに応える始末。How are you?ーI am beautiful。
中学校英語教育は異なる文法が世界には存在することを知らせるのが目的だったはず。愚にも付かない英語の挨拶をおぼえさせるのが最近の英語教育らしい。故加藤周一が指摘したように,英語の授業では「読み」に力を入れることが重要で大学生でさえ英字新聞をロクに読めないと嘆いておられた。これからはChatGPTの時代。翻訳は自由自在。世の中ずいぶん変わった。してみると英語教育の目的は何か。
大学入試にアメリカ発の教材が使える,使えないかの騒動があったが,日本人はまず自国語で,日本語で読み書きが自由にできなければ日本人としての誇りがもてないだろう。ChatGPTの登場によりかえってそういう時代になった。
中国の科挙を見習う必要はないがたとえ新自由主義やChatGPIが日本に上陸しようとしまいと,日本人なら日本語で読み・書き・話すことができなければならないだろう。それが日本人の矜持というものである。そしてその次に外国の一つや二つを読んで理解できる人間になることが大切である。
日立には教育工場という社員教育の場がありましたが、それはあくまでも社会人である社員へ必要な知識を叩き込むためのものだったと思います。学校教育とは全くの別物です。会社組織の歯車(あるいはネジ)作りのためのものです。
子どもたちの可能性を見極め、広げ育てることをやらずに、最初から社会の歯車づくりを行う事を目標にするというのは全く狂っているとしか言いようがない。