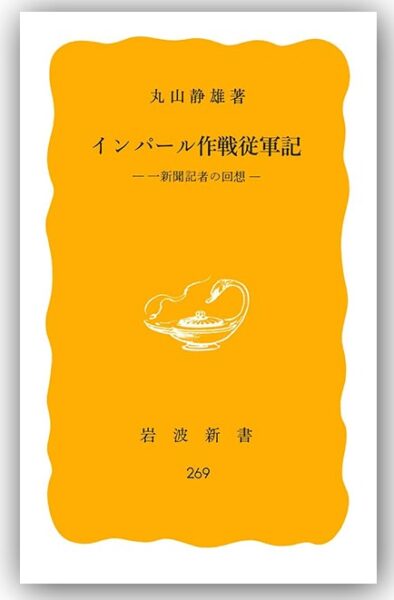 著者は戦時中、『朝日新聞』記者としてインパール作戦の従軍記者となり、最前線で取材に当たった人物だ。インパール作戦はビルマの山中に若い日本兵のおびただしい数のしかばねをさらし、著者は死線の中をかろうじて生還した。それから40年経った1984年、「早くも戦争を過去の出来事として忘れようとし、軍備を増強し、仮想敵国をつくって敵対意識を煽り立て、再び戦争への道を歩みつつあることに危機感を感じ」、この本を著した。そして戦後80年の今年、岩波新書クラシックスで復刊された。
著者は戦時中、『朝日新聞』記者としてインパール作戦の従軍記者となり、最前線で取材に当たった人物だ。インパール作戦はビルマの山中に若い日本兵のおびただしい数のしかばねをさらし、著者は死線の中をかろうじて生還した。それから40年経った1984年、「早くも戦争を過去の出来事として忘れようとし、軍備を増強し、仮想敵国をつくって敵対意識を煽り立て、再び戦争への道を歩みつつあることに危機感を感じ」、この本を著した。そして戦後80年の今年、岩波新書クラシックスで復刊された。
インパール作戦とは、1944年3月8日、ビルマ(現ミャンマー)に侵入・占領した日本軍の3個師団と軍直轄部隊、合計8万5600人の兵士によって実行された。米英政府の蒋介石支援ルート(援蒋ルート)を遮断して重慶政府を孤立させ、日中戦争を有利に進めるとともに、ビルマ国境をこえてインドに侵攻し、インドの反英闘争と連携しつつイギリスを撤退に追い込むという、夢想に満ちた作戦だった。
しかし、著者が何度も指摘しているように、この時点で太平洋戦争における日本の敗戦は明白だった。だが、天皇をはじめ権力中枢はみずからの地位を守ることを第一に、ズルズルと戦争を続けていた。
インパール作戦で日本軍は「意表をつく奇襲によって、一挙に英印軍を壊走させる」つもりだったが、作戦は英印軍に見破られ、待ち構えられて「有史以来最大の敗北」を喫する。その後、武器弾薬も食料も尽き果てた日本軍の壊走に次ぐ壊走となる。
著者は作戦失敗の原因として、自然(雨季)の無視と補給の無視をあげている。インパール作戦は、「糧秣は現地調達」といってわずか20日分の食料だけを携行して行動を起こした。しかし、進路は原始未開の山岳・密林地帯で、調達しうる食料はなく、航空機の支援も期待できなかった。第31師団の佐藤中将は、いたずらに兵士の死者を増やすような無謀な作戦に抵抗し、独断で1個師団を率いて戦線を離脱し、補給を受けられる地点まで下がった。前例のないことである。
また、牟田口将軍はジンギスカンの故事に習い、牛約3万頭、馬1000頭を調達して輸送力にしようとしたが、大河チンドウィン川で流され、また密林の通過に慣れておらず、兵士は飢えのあまり牛を食料にした。
著者はこうしたことから、インパール作戦は「無用の戦い」、やる必要のなかった戦争と断じている。
牟田口将軍は同年4月の天皇誕生日に最後の総攻撃をやろうとしたが、すでに兵力の損耗、士気の乱れ、統帥の破綻は激しく、総攻撃は中止されて退却に転じた。退却となると、英印軍の追撃を振り切って、東進してカボウ谷地に逃げ込み、さらに再びチンドウィン川を渡らなければならない。しかし、いまや雨季となり、河は大増水し、舟もない。
退却する兵士たちはカボウ谷地に殺到した。チンドウィン川の西岸に細長く南北に伸びる谷地は、敗れ、傷つき、病み、雨に打たれ、泥にまみれた将兵の白骨街道と化した。大本営がインパール作戦の中止を決定したのが同年7月3日だが、その後も日本兵の「死の彷徨(ほうこう)」は続いた。
飢えや病気でばたばたと
著者は、みずからが見た白骨街道の様子をこう書いている。
「見れば、そこここに兵士の死体が横たわっていた。死体は、すでに白骨と化したもの、腐乱し始めたものから、一瞬前に自ら生命を絶ったのであろうか、まだ蝿さえついていないようなものまであった。シャツの心臓部に血がにじみ、両眼を見開いていた。足下に血のついた小銃が転がっていた。おやっ、頭がないと思って近づいてみると、首から上には蝿が真っ黒にたかっていた。死体は山渓の片側に点々と続いていた。倒木によりかかるように、あるいは立木に身体をもたせかけて眠るように息絶えている者もあった」
顔見知りの兵隊が牛歩で進んでいるのに出会い、心配して面倒をみたが、やがて倒れて動かなくなった。「マラリア、脚気、飢餓、まさに死の一歩手前にある兵隊が完全軍装を身につけて戦場を下る、肩いからすのでなく、時に“シャレ”をいいながら――なにか生命をかけて軍隊というもの、戦争というものに対して抗議する、兵隊の精一杯の抵抗の表現のように思えた」
カボウ谷地の所々には「野戦病院」があり、身動きできない重傷患者が「遺棄」されていた。回復の見込みのある者は、戦友が木の枝と竹で担架をつくって担いでいったが、そうでない者は手榴弾と薬を持たされて置き去りにされた。
モレーの野戦病院の様子についても、こう書いている。「熱帯マラリアで狂い死にする者。1日40~50回もトイレに行く赤痢患者。薬品はない。前線からは下ってくるが、後方に送る手段がなく、病院には患者が溢れる。うめく者、目を見開いたまま、すでにこと切れた者。生きているのか、息絶えたのか、顔を雨に打たれたまま黙然と目をつむる者、いずれも顔は生気を失い、あたりには死臭と糞便の臭気がただよう」
奇跡的に前線から脱出した著者は、マラリア、赤痢、栄養失調でやせ衰え、1カ月間死んだように眠ったという。「敗走千里」というから4000㌔を歩いたということか。その後、ラングーンの野戦病院に知人を見舞った。そのときの様子をこう書いている。
「顔が土色で、手足の皮膚は象のそれのように灰色に黒ずんで、しわが寄り、骨と皮のような患者はインパール方面から来た兵隊だった。南西沿岸方面の患者も、雲南方面の患者もやせ細っていたが、インパール方面の患者に比べると、やせ方はまったく違っていた。また、他方面の患者はそれなりに携行品があったが、インパール方面の患者は靴すらなく、せいぜい小さな風呂敷包み一つがある程度だった。一番大きな差異は、インパール方面の患者の目に生気のないことだった」
こうしてインパール作戦で戦死、または戦傷病死した兵士の数は、4万とも、6万ともいわれる。こうした事実を前に、先の大戦を「聖戦」だとか「日本を守るための正義の戦い」といって美化することができようか。
著者は、戦争を始めた国家権力への憤りと、反戦平和への強い思いを込め、みずからの体験を残しておかなければならない社会的責任からこの本を書いたとのべている。この本の最初の刊行は1984年6月であり、中曽根内閣が「日本列島不沈空母化」を打ち出し、大きな反対世論が巻き起こった時期である。そして、ふたたび軍備強化がもてはやされる今、当時以上に戦争の実体験から学ぶ意義は大きくなっている。
(岩波新書、222㌻、定価1020円+税)





















