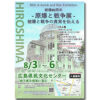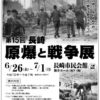(2025年8月6日付掲載)

「原爆と戦争展」の展示パネルを見る参観者たち(3日、広島市中区、広島県民文化センター)
被爆80年目の広島で「原爆と戦争展」(主催/原爆展を成功させる広島の会、6日まで)が開催されている。第2次大戦末期の1945年8月6日と9日、米軍が広島・長崎に投下した2発の原子爆弾により、瞬時に数十万人もの人々が無残に焼き殺され、生き残った人々も放射線障害によって次々と命を奪われた。あれから80年の節目の年を迎え、直接被爆体験を語れる世代が90歳前後になるなかで、残された被爆者たちが被爆の実相とともに被爆地市民の願いを次世代に語り継ぎ、若い世代もその思いを背負って積極的に伝承活動に参加し始めている。体験者世代が減少し、戦争を知らない政治家による観念的な歴史修正や核武装を含む議論まで飛び交う一方、原子雲の下にいた市民の叫びを市民の手で発信するとりくみがひときわ強い共感を集めている。
会場の広島県民文化センターでは、広島・長崎の被爆の実相を被爆者の体験に沿って構成した「原爆と峠三吉の詩」パネルを中心に、「みんなが貧乏になって戦争になっていった」に始まる戦前の経済恐慌、満州事変から15年に及ぶ日中戦争、餓死や病死で次々に兵士が斃(たお)れていった南方戦線、学徒動員、真珠湾攻撃とアメリカの対日参戦、全国空襲、沖縄戦にいたるまで、体験者の証言や各種資料で時系列に編集したパネル約140枚(英訳付き)が展示されている。
また、20年間にわたる展示活動のなかで広島・長崎の市民から寄贈された体験記、絵、軍服や軍靴、出征兵士に贈られた日の丸の寄せ書き、千人針、慰問袋などの実物資料も手にとって見ることができる。戦中戦後の広島を記録した写真集や絵本なども多数とりそろえ、親子連れから子どもまで世代をこえて学べる場となっている。
会場では連日、広島市内の被爆者たちが体験を語るとともに、被爆二世や若い世代による伝承朗読(身内や知人の被爆体験をまとめて語り伝える)を新たな試みとしておこなっている。被爆した親たちが鬼籍に入るなか、遺言ともいえる被爆体験と平和の思いを受け継ぎ、世代から世代へ繋いでいく営みがくり広げられ、「生の被爆体験を聞きたい」「次世代として何ができるのか考えたい」「教師として子どもたちに教えるうえでも実体験に触れたい」と親子連れや教員、市民たちが真剣に耳を傾けた。
90代の被爆者力強く語る 真剣に耳傾ける若者

若い世代に被爆体験を語る被爆者(6日、広島県民文化センター)
17歳のときに被爆した本谷量治氏(97歳)は、広島駅近くの国鉄の印刷工場で働いていたときに被爆した経験とともに、市内中心部の薬研堀で暮らしていた母、姉、弟2人の家族全員が原爆で亡くなったことを言葉を振り絞るようにして参加者に語り伝えた。大阪で70年住んでいた本谷氏は被爆体験を語ってこなかったが、数年前「原爆と戦争展」に参加したことをきっかけに体験を語り始めた1人だ。
本谷氏は、学校卒業後、広島駅付近の鉄道局の印刷工場で働いていたが、8月6日、職場に出勤してラジオ体操をし、朝礼で職場長の話を聞いているとき、突然「ピカッ!」という青白い光が走り、「何事か」と思っているうちに、崩れてきた建物の下敷きになって意識を失った。気がついて「助けてくれ!」と叫んでも誰もおらず、薄暗がりのなか、右目と右手にケガを負いながらも外に這い出た。職場は燃え、東練兵場では火傷でふくれた兵隊たちが「水をくれ!」といいながら転がっていた。
避難した二葉山から見ると市内は一面真っ赤に燃えていた。「わが家ももうダメだな…」と思った。翌7日、薬研堀の自宅に向かったが、まだ地面には熱がこもり、わらじを履いていても足の裏が熱かった。自宅は父が生前につくった五右衛門風呂の釜だけを残して燃え尽きていた。
家にいた母と弟は、海田町(爆心地から約8㌔㍍)に避難していて無事だったが、爆心地近くの燃料会館(現在のレストハウス)働いていた姉(19歳)は10日後に白血病で他界。学徒動員で建物疎開の作業に出ていた下の弟(12歳)の行方はわからず、母親と一緒に川沿いを歩いて探したが見つからなかった。川の中では死んだ人が浮いたり沈んだりしており、救護の人たちが引き上げて廃材を使って焼いていた。そのなかに弟もいると思い、母と一緒に手を合わせた。弟の遺骨は今も見つかっていない。
「8月の末頃から、無事だった母(52歳)も上の弟(14歳)も体調が悪くなり、動くとすぐに倒れるようになった。2人とも髪の毛が抜け、体中に紫色の斑点が出た。ドクダミの葉を飲ませたりして看病してもよくなることはなく、弟は9月6日の朝に息を引きとった。そのことを母には伝えることはできなかった。そのうち母も、朝鮮半島から復員した兄の顔を見て“あぁ、これで安心だ…”といって息を引きとった。9月8日だった。私が母の遺体を焼き場に運んで焼いた」と涙をこらえながら語った。
「9月20日から私も体調が悪化し、40度の熱が出て寝込むようになった。枕元で親戚が“この子ももう長くないのでは…”と語っているのが聞こえた。自分も髪が抜けないか、身体に斑点ができていないかを毎日確認する日々だった。なんとか回復して、20歳で大阪に働きに出たが、肺結核、急性肺炎などの病気を患い、小学生のときは無欠勤で表彰されるほど丈夫だった体も原爆から弱くなった。10年前には胃癌、膀胱癌、腎臓癌にもなった。戦争はダメだ。戦争をやれば小さい子どもも働かなければならなくなる。戦争は絶対にやってはダメだ。私も生きているうちは戦争反対を訴えていきたい」とのべた。
10歳で被爆した研岡英夫氏(90歳)は、自身の体験を描いた絵をパソコンにとり込み、テレビ画面に映しながら証言した。「当時、嚶鳴(おうめい)国民学校(爆心地から約1㌔㍍の位置にある現在の古市小学校)の5年生だったが、学校では軍馬にやる草を刈って運動場で干す仕事をしていた。8月6日は雲一つない晴天で、校長先生の話も終わる頃、南の空がピカッと明るくなり、太陽よりも黄色い光に包まれた。校長先生が“すぐに校舎へ行け!”と大声で叫んだが、それも間に合わないうちに爆風で大きな噴煙が上がった。私たちは目と耳と鼻を押さえて身体を伏せたが、爆風が校舎にぶつかってガラスが割れ、子どもたちの悲鳴が聞こえてきた」と当日の様子を語った。
南の空には大きな黒い雲がのぼって迫ってくる。それが後で「きのこ雲」だと知った。家に帰ると両親が待っていた。兄弟たちはみな市内に働きに出ていたが、宇品線の電車の中で被爆した次姉は、つり革を握っていた手が閃光を浴びて火傷を負い、両手からボロ雑巾のように皮をぶら下げて帰ってきた。16歳で己斐に学徒動員に出ていた兄は、全身大火傷をして帰ってきたが、蝿がとまってウジが湧き、箸でつまんでとり除いても間に合わないほどだったという。
「長兄を探して横川橋までたどりつくと、八丁堀までの焼け野原が一望でき、中国新聞社屋や福屋百貨店のビルを除いて瓦礫になっていた。本川沿いには材木の筏(いかだ)が係留されていたが、その間に水を求めた人たちが寄り添うようにして死んでいた。親戚の家があった現在の平和公園は、映画館や芝居小屋が建ち並ぶ広島一の繁華街だったが、無残な焼け野原で人も建物も何も残っていなかった。その後は学校の校庭に穴を掘って死体を埋める作業をやっていた。私ももう90歳だが、あの悲惨な出来事を風化させてはいけない。被爆の体験と核兵器の恐ろしさを子孫や世界中の人に知ってもらうことが今を生きる者の使命だと思い、証言させていただいた」と聴衆に訴えかけた。
次世代による伝承朗読 「感情や思い伝える」

被爆者の体験談を聞く参観者たち(6日、広島県民文化センター)
東広島市の女性(50代)は、これまで次世代としての被爆体験継承を模索し続け、今回の「原爆と戦争展」で初めて伝承朗読をおこなった。母親の同級生である男性被爆者(87歳)から断片的に聞いてきた体験を今回改めて聞きとり、「人前で話すことには慣れておらず、体力に自信がない」という本人にかわって次のような内容の手記を朗読した。
男性は当時、広島市内の広瀬北町に家族6人で暮らしており、産業奨励館(現在の原爆ドーム)に出かけたり、停車中の路面電車の中で遊ぶような平和な日常を送っていたが、原爆はそれを一瞬にして地獄に変えた。爆心地から1・1㌔の広瀬北町はほとんどの家が倒壊・焼失し、学区内での死者は5000人以上。広瀬小学校の児童の大半は田舎に疎開していたが、8月6日に登校した生徒、教師あわせて100人余の命が失われた。
小学生だった男性は島根に疎開していたが、8月6日に広島の親戚から「広島は全滅」との知らせを受け、家族を探すために叔父に連れられて広島に入市。一面が焼け野原で自宅がどこにあったのかもわからず、家族との再会も果たせなかった。橋の下で聞いた「助けてくれー」「水をください」など、たくさんの人々のうめき声が今でも忘れられない。
その後、広島市東千田町の広電車庫で働いていた兄が島根に戻ってきたが、爆風で飛んできた瓦が頭にあたり17針縫う大けがを負っていた。8月10日ごろ、父が三篠小学校に収容されていることがわかり、兄と姉が会いに行ったが、看護師から「もう30分しかもたない」といわれるほどの重傷だった。
全身に大火傷を負って瀕死状態だった父親は、自宅で被爆し、母も母屋の下敷きになったが探し出すことができず、自分は火の海の中をふとんを被って避難し、広瀬川に飛び込んで命からがら小学校にたどり着いたと話し、息を引きとった。近くの農家から薪をもらい、17歳の兄と14歳の姉が2人で父の遺体を焼いたという。
戦後、原爆で親を失った兄弟は親戚の家に別々に預けられ、男性も親戚の家を転々としながら生活した。寝たきりのおばさんの面倒を見ながら、水道がないため毎日井戸水を汲み、お金を稼ぐために鉄くずや金物を拾い集めてその日の糧にしていた。学校に行くこともできず、食べ物がないため畑のミカンを食べて空腹を満たしていた。
「原爆で両親を亡くしたときの辛さより、戦後、生きていく方が本当に辛く、必死だった。戦争さえなければ…原爆さえなければ…。誰一人、私のような辛い思いをしてほしくない。させてはならないと強く思う」――そう締めくくった。
朗読を終えた女性は「この被爆者の方は、小学生のときの話をされるとき、いつも強く訴えかけるように涙ぐんで話をされる。話をしてくださった被爆者の方の思いを、亡くなられたすべての方の思いを私を含む戦争を知らない世代に伝承していきたい。私の母も入市被爆し、被爆者の救護で傷口のウジを取ったりしたと聞いていたが、改めて聞こうと思ったときには認知症を患って聞くことができなかった。そのため2年前から母の同級生の方から被爆体験を聞き、それを伝えていくことにしたが、伝える側になって知らないことの多さを痛感した。知識としての原爆ではなく、被爆者の方々が胸に抱いてきた感情や思いを伝えていきたい」と話した。
同じく81歳の被爆者にかわって体験記を朗読した20代の女性は、聴衆から「憲法改正などの無気味な動きに対してどう対処していけばいいか?」という問いに対して、「私には戦争の体験もないし、戦争当時の国家総動員法の話を聞いても、国民みんなが一つの方向を向くような事態が起きることなど信じられなかった。でも、新型コロナの時期、自由な行動や人との接触ができなくなり、あらゆる行動を自主規制しなければならないという圧力を強く感じた。個人の自由が利かなくなる社会は簡単に起こりうることを実感した。戦争にも同じ原理で向かっていくのではないかと思う。だからこそ、与えられた情報が本当にみんなのためになるのかを考えたり、身近な人たちを大切にしていくことから、戦争ではない解決の仕方を常日頃から考えていくことが必要ではないか」と話した。
会場内で体験証言や伝承朗読が始まると、次第にそれを聞く人たちの輪が広がり、証言会が終わった後も、被爆者を囲んで当時の体験に対する質疑応答や戦争情勢に対してどのような活動が必要なのかを語り合う交流の輪が生まれている。
参加者の一人は「被爆伝承朗読は、原爆の体験や実態を伝える一つの手法として大切だと思った。本谷さんの実際の体験談はあまりにも強く、圧倒的なものだった。被爆体験者もいつかはみんないなくなってしまう。そのとき、朗読も含めてあらゆる伝承活動をどうやっていけばいいか、より良い手法や形式を常に考えたい。それを日本だけでなく、世界で展開してほしい。広島に関心をもって来てくれる人だけでなく、あまり関心がない人たちの日常に、目に触れる機会が必要だと思う」と感想を記した。
戦争を許さぬ思い 若い世代も受け継ぐ意欲
広島在住の女性は「ひとたび戦争を始めてしまうとなかなか終えることができない。戦争に勝った者が正義となるからだ。現在のパレスチナの問題でも、イスラエルは“パレスチナに飢餓はない”といい張っている。戦争の仕方にもルールがあるが、勝つためにそれらが無視され、無差別の殺りくとなる。原爆を投下したトルーマンも“軍事基地である広島に原爆を落とし、破壊することに成功した”と発表したと聞く。国民の多くは兵隊としてかり出されたり、銃後の苦しい生活、つらい勤労奉仕を強いられたが、それを強いた政府や軍部の指導者たちが戦後どのように立ち回ったのかをもっと知らせるべきだと思う」と感想を記した。
広島市内の30代の父親は2人の子どもを連れて参観し、「広島では原爆のことについて触れる機会は多いが、全国でこれほどの空襲がおこなわれていたことなどは知らなかった。子どもの頃から“日本は悪いことをした”という教育を受けてきて、戦争を考えることが嫌になっていた時期もあったが、この展示を見るとその考えを改めなければいけないと感じた。祖父の兄はサイパンで玉砕しており、先日初めて家族でサイパンに慰霊の旅に行った。現地の人たちに恨まれているのではないかと不安だったが、とてもよくしていただいた。何が起きていたのか、本当のことを知りたい」と涙を浮かべて語った。
「これまで核武装という話を聞いて納得する自分もいたが、この展示を見るとそんなことを口に出すことすら罪悪感を感じる。戦争で亡くなった人たちを弔うことを戦争の正当化と同列視してはいけないと感じる。戦争を体験した人たちの存在によって歯止めが利いていたことが、今後その人たちがいなくなった後にその抑止力がなくなり、私たちの世代がどうやって戦争を防ぐのかを真剣に考えないといけない。92歳の祖母も広島で被爆しており、今のうちに子どもたちと一緒に話を聞きたいと思う」と話した。
千葉県から訪れた59歳の会社員男性は「ここに来る前に原爆資料館に行ってきたが、この展示を見てより心に迫るものがあった。あの戦争を回避する知恵がなかったのだろうかと痛切に思う。この展示には下関出身者の証言が多かったが、自分の母も下関出身で、戦中戦後の物がない時代の話を子どものころから聞かされてきた。母がいっていたこととまったく同じだった。叔父も南方で戦死しているため涙が出てくる。本来、民主主義というのは多様な意見が尊重されるため戦争が起こりにくいシステムであるはずなのに、現在はそれがないがしろにされている。現在、保守を標榜する“エセ保守”の人たちはそれを破壊する国賊だと思っている。この展示は子どもの時期から伝えるべき内容だ」と感想をのべた。
新潟県から訪れた28歳の男性教員は「初めて広島に勉強しに来た。小学生を相手に歴史のことも教えてきたが、これまで何も知らずに教えていたことを痛感した。実際に現場に来て、この目で見て、被爆者の方のお話を聞かなければ何もわからないと思った。帰ったら子どもたちに伝えていきたい。新潟では原発問題(柏崎刈羽)がよく取り上げられるが、なぜそれが危険なのかを考える原点は広島にある。書物やネットで得る知識と実物を見て得るものはまったく違う。実際に現場に来て抱いた感情を含め子どもたちに本当のことを伝えたい」とのべた。
沖縄から夫婦で訪れた観光ガイドの女性は「被爆80年の広島と長崎に来て、どんなことがおこなわれているのかを学びに来た。戦争全体のなかで沖縄戦や原爆について考えることが大切だ。現在の沖縄では“戦後”とはいえない現状がある。沖縄本島だけでなく南西諸島でも自衛隊ミサイル基地がつくられ、それも経済的な振興策とセットで持ち込まれるため、自衛隊配備の是非を論議することすらできない。軍が入ってくれば嫌でも緊張感が生まれ、日々のニュースでも中国と敵対させるように誘導する情報だけが流される。また沖縄が戦場にされるという危機感を肌身で感じている」と話した。
さらに「自衛隊は米軍とは違って災害などから国民を守るという名目で沖縄に浸透していたが、今では米軍の尖兵のような扱いで最前線に立たされようとしている。住民の生活やコミュニティがないがしろにされ、“国の安全保障のため”といって軍備が最優先になりつつある。だからこそ沖縄戦での日本兵による住民弾圧の記憶が呼び覚まされている。展示からは事実や知識だけでなく、そこにいた人々の思いが伝わってくる。戦争を止めるためには、その思いを受け継ぐことが一番大切だと思う」とのべた。
同伴した男性も「戦争が沖縄だけの問題ではないことがよくわかる。いったん戦争が始まれば、局地戦では終わらず、日本中が壊滅する。だからこそ、それを防ぐために外交や文化交流などで緊張を緩和することが必要なのに“中国が○○した”という情報だけが一方的に流されて、友好的な活動がやりにくい雰囲気が作られている。それに若い人たちが流されていかないか心配だ。最近の選挙でも“英霊が!”といって戦争を賛美する若い政治家が多く見られたが、“あなたたちは本当のことをどれだけ知っているのか?”といいたい。広島でこのように誰にも遠慮なく真実を伝える展示活動に出会えてうれしい」とのべた。夫婦とも「ここで学んだことを沖縄での平和ガイドの活動に生かしたい」とパネル冊子を持ち帰った。
海外からの参観者も目立っている。ニュージーランドから来日した20代の男性は「世界で戦争が起きており、とくにパレスチナ問題では国内でイスラエルに対する抗議デモが頻繁に起きている。ニュージーランドは直接の戦争被害は少ないが、入植者と先住民との争いやアメリカの同盟国として戦争に軍を派遣してきた歴史がある。原爆やその後のベトナム戦争の被害を知るにつれ、アメリカの正義とは本当の正義なのか? なぜこれほどに人を殺す必要があったのか? と強い疑問を感じてきた。原爆投下は戦争を終わらせるためには必要のないものだったし、今でも原爆の使用を正当化するアメリカ政府の考え方には反対だ」と語った。
また「戦争を起こさないためには、国や宗教の違いをこえて平和のために相互に尊重することが必要だが、そのうえでも広島は素晴らしい場所だ。広島市民はこれほどの被害を受けながら、それを乗り越えて街を復興させ、“やり返せ!”ではなく、二度とこのような悲劇をくり返させてはいけないという発信をしている。これは世界中が学ぶべき姿勢だ。私が広島に惹かれる理由でもある。母国では原爆について学ぶ機会は限られているので、いつかニュージーランドでもこのような展示をやってほしい。必ず歓迎されるはずだ」とのべて、スタッフに握手を求めた。
カナダ人の男性は「非常にパワフルな展示だ。原爆について学ぶために初めて広島に来たが、ここには生存者の声が凝縮されている。それを知ることは非常に大切なことだ。カナダでは史実としての原爆投下は教わることはあっても、それによって何が起きたのかを教わることがない。私たちは核も戦争もない時代を作らなければいけない」とのべた。

長崎市民が描いた被爆体験画も展示された(広島県民文化センター)
「生きた声」を受け継ぐ アンケートより
▼今年の原爆と戦争展は、原爆の実態に迫るうえで広島原爆資料館以上のインパクトがあると思う。それは峠三吉の訴えによるものが大きいと思う。原爆の被害、戦争の実態を人々に伝え、平和な社会を築くためには、戦争に至る過程、政治的な背景を学ばなければならないと感じる。(広島県・71歳・男性)
▼私は1945年8月3日に八王子で空襲に遭った。八王子の街はみんな焼けて、道だけがあった。10月に広島市内を歩いた。台風で橋が落ちていた。広島の街はみんな焼けていて、白い道だけがあった。その道を人々が歩いていた。
友人に大阪で空襲に遭い、孤児になった人がいる。戦後の「たずねびと」の番組で両親が見つかった。浮浪児と呼ばれ、食べ物を探していろんなことをしたと言っている。なぜ大人は自分のことばかりで子どもの救済をしなかったのだろうか。
広島県では参政党が3位の票を集めた。参政党は日本が原爆を持つことに賛成している。なぜ広島であれほど票を集めたのか解らない。(広島市・85歳・男性)
▼被爆80年。多くの戦争体験者が亡くなるなかで、伝承できる方も減少し、次の10年では実際に戦争を体験した人はほとんどいなくなる。ただ、世界中の紛争や対立はまったくなくならず、むしろ核兵器使用の危機は現実的なものになっていっているように感じる。広島で生まれ育ち、今年は仕事の関係で多くの広島・長崎に関する資料を見て、実際つくる側にもなった。世界の人が平和を願い、核兵器がゼロになる世界を望むような優しい世界になればいいと思う。(広島市・女性)
▼とにかく事実は隠されていて、ほんの一部しか知らされていないことを実感した。学生には考える教育を、一般人には考える営みを求める。(79歳・男性)
▼米軍のルメイ少将の文民密集地帯に対する攻撃の論理は、現在のイスラエルのガザ攻撃の論理とまったく同じだと思った。歴史はくり返す…。(無記名)
▼被爆者本人、また伝承者の方のお話を聞くことができて、とてもよかった。一人一人の生活・人生を感じることができた。次世代の若い方が伝承者になられていることはとても心強い。また、個人的にもお話をし、伝承者の方も心に揺るぎない信念を持たれている。これは原爆と戦争展スタッフの方々にも感じられる。とても大切なことだと思う。戦争は絶対にあってはならない。平和とは何かを改めて考えたい。次回からも証言や伝承を聞く会を設けてもらいたい。(広島市・63歳・男性)
▼兵隊になる人がいなくなれば、軍隊はできない…と思っていたが、ドローンや無人機などで戦争をする時代になってしまった。攻撃する側に人的犠牲がなくなると罪悪感もなく、事態は深刻化している。「戦争」と呼ばない“殺りく”がまかり通る時代になってしまった。原爆をつくりだした人間と、その心理・葛藤などを理解する努力をしなければ、兵器の怖さのみを訴えても決してなくならないと思う。(61歳・男性)
▼年々、戦争の足音が近づいているような現代は、新しい戦前などという人もいる。子どもの頃からわれわれが学んできたはずの平和教育とは何だったのかと暗鬱な気持ちになる。今ならまだ間に合うはずだと信じたい。(横浜市・57歳・会社員男性)
▼竹屋小学校、国泰寺中学校を卒業した。広島で生まれ育ち、戦争や原爆について学んで来ていたつもりだったが、改めて本日のこのような展示を拝見し、平和に対する思いが強くなった。年々高齢化されていく被爆者たちの「生きた声」を大事に、後の世代に語り継いでいく必要があると思う。8月6日は広島の人たちにとっては忘れてはならない大事な日だ。もっとたくさんの若い世代に知ってもらうためにこのような場を各地で催していただきたい。(47歳・女性)
▼現在の戦争について、過去の過ちと反省があるはずなのに、それから学んでいるはずなのに、なぜまた戦争をするのか? 武力ではなく話し合いで解決できないのかと残念だ。究極、平和とは人を殺す、殺させる戦争をなくすことが大事だと思う。自分になにができるのか考えていきたい。私自身も親が原爆・戦争体験者だが、それからどんどん世代が進み世代間の感じ方の違いがあるかもしれないので、若い世代へのアピールがもっと必要だ。平和について明るい未来を託したい。(広島県・66歳・女性)
▼問題解決をするために、戦争という選択肢があること自体がおかしい。誰もが自分の利益、国の利益を守りたい気持ちは分かるが、その解決策が戦争や暴力では絶対にいけないということをすべての人が肝に銘じなければならない。人の命より大切なものはない。原爆投下の事実を風化させてはならない。戦争は二度と起きてほしくない。核をなくす方向へ賢人が行動をおこさなければならない。(広島県・63歳・女性・パート)
▼子どもの頃にはあまり知ろうとしてこなかったが、私自身が親になり、私が暮らすこの日本で何が起こっていたのか知らないといけないと思うようになり、テレビや戦争展を努めて見るようになった。日本がこれまでにたどってきた道は、本当につらく厳しいものだった。胸が締め付けられるような写真や言葉がたくさんあった。
私に何ができるか? 何もできないが、少しでも心を寄せることができたらと思う。未来を作る今の子どもたちにも、辛くても事実を少しずつ知ってほしい。そして過去と同じ過ちを繰り返さないような日本の国民であってほしい。もちろん私も。(広島県・54歳・主婦)
▼教育の大切さを痛感している。自分の頭で考え、自分と、自分以外の人も幸せに生きるために、何をするのかを考え続ける力をつけなければならないと感じる。貧しくなり、考える余裕のない大人が多いなか、戦争は近づいてきている。文句をいうだけでなく、考えたことを伝えて、行動できる人が増えれば世界は平和になるのではないか。自分ファーストではなく、三方よし、自分も周りも幸せになるために。(滋賀県・52歳・女性・教員)
▼母が横川で被爆している。いろいろな持病を抱えながら2022年7月、79歳で他界した。戦後の差別はとてつもなかったようで、友人付き合いや結婚もすべて周囲の目で制限されていたそうだ。今日の体験談の中でも差別の話があり、母は懸命に生き抜いたのだと思った。幼少期をアメリカで過ごした日本人の友人は戦争に対する真逆の感覚を持っている。争いでの一番の被害者は市民だ。洗脳するのは軍部(政府)だ。現在も世界中で戦火が上がっている。すべての国の民が争いを求めていないはず。どうか自己利益のための争いはやめてほしい!(50歳・女性)
▼久しぶりに原爆と戦争展に来た。自分の生活のなかでも、多忙さを理由に戦争の過去・現在・未来について考えることも少なくなり、また、ウクライナやガザなどの戦禍の状況に、自分の無力さに、世界の状況に対して以前よりも悲観的になっていた。しかし今回、今さらではあるが実相を知ること、そのことを若い世代に伝えることこそが重要なことだと思いを新たにした。(京都府・男性・教員)
▼実際に当時の写真や記事の展示を見て、教科書やいい伝えとは書きぶりが違い、より当事者視点で戦時の状況を感じることができた。子どもたちと平和について学んでいく者として、これからも多くの情報に触れ、正しい知識を身につけ、戦争・兵器廃絶に向けて考えていきたい。貴重な経験になった。また広島に来て、いろいろな場所を訪問してみたいと思った。(三重県・29歳・男性・小学校教員)
▼これらの記事はどんな時に読んでも、反戦の気持ちがわき上がってくる。戦争は、国のすべてを消費して目標遂行しようとする外交手段だ。しかし、それは勝っても負けても国民からすれば地獄そのものだ。自身の祖父が長崎で空襲に遭い、命からがら生き延びた。悲惨な戦争はもう繰り返したくない。二度と繰り返してたまるか。その決意が固くなった。今後、機会があればボランティアに参加したい。(山口県・21歳・男子学生)
▼戦争が、原爆がどれだけの人を苦しめたのか。どれだけ悲惨だったのかということを原爆投下日の3日前に知ることができ、平和がどれだけ素晴らしいことなのかを改めて実感できた。戦争を起こさないために広島の悲劇を全世界に伝えることが必要だと思った。チラシをいただいて、急きょ友達と来ようと思い、来させていただいた。関心のある人を増やし、知ってもらうためにテレビで放映してほしい。(17歳・女子高校生)
▼背中などにガラスややけどなどがあった人や、ひばくして、顔が変形したりしていた人がいて自分もこんなことが起きたらこわくて、耐えるのも難しいと思ってしまう。戦後80年より後も、このような展示を開催して、いろいろな人にひばくのことについて話して外国の人にも伝えていってほしい。(広島県・11歳・女子小学生)

広島平和公園の原爆の子の像付近でも同じパネルを使用した街頭展示がおこなわれ、国内外の人々が多く参観した(3日)