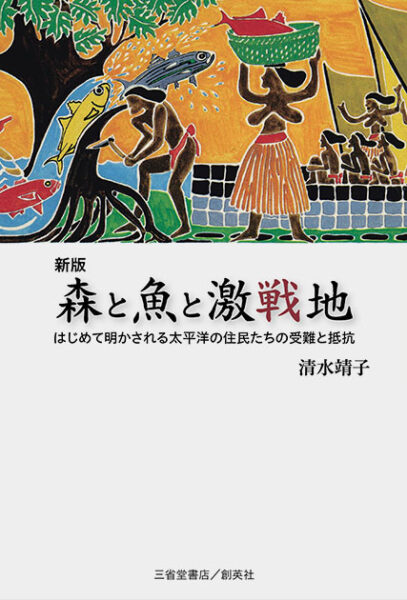 「かつて日米の戦いの激戦地だった太平洋。その海と島々は今、環境破壊の激戦地になっている」
「かつて日米の戦いの激戦地だった太平洋。その海と島々は今、環境破壊の激戦地になっている」
この本の著者は1937年生まれで、メルセス会修道女会に入会し、日本の高校で11年間社会科の教師をした後、1980年からグアムとサイパンに派遣され、現地の高校で教えてきた人だ。それから今日まで彼女は太平洋の島々をめぐり、ボートで現地の人に案内されながら、また小屋で現地の女たちと雑魚寝しながら、ときには森林伐採企業の雇う私兵に追いかけられながら、たくさんの聞きとりをしてきた。それは、そのまま埋もれさせておくにはあまりにももったいない話ばかりだったという。
そこからできたこの本は、太平洋戦争の時期に現地の住民たちが何を経験したのか、そして戦後は日本を含む多国籍企業が現地でなにをしており、住民たちがどのように抵抗しているのか――を中心に、日本の市民、とくに若い世代に語りかけるものになっている。どの章の話も初めて聞くことばかりで、驚きの連続だ。
印象に残った一つはパプアニューギニアのラバウルをめぐる話である。

大本営のラバウル侵略計画は、トラック島の連合艦隊基地を守るための前進基地建設が目的であり、侵攻・占領後は陸軍と海軍が司令部を置き、敗戦まで10万人もの兵士がいた。この日本軍占領下で、現地のトーライ民族(4000人)、華僑(1200人)、徴用・徴兵されてきた1万人をこえる軍属(朝鮮人や台湾人)、連行されてきたシンガポールなどからの8000人の捕虜(インド人、インドネシア人、マレー人、中国人)らが、日本軍の洞窟陣地や飛行場建設、食料生産のための奴隷労働を強いられ、飢えと病気と、日本軍による処刑の恐怖にさらされながら日々を過ごしたという。
地元の人から、日本軍が村の住民に掘らせた洞窟陣地を見るように勧められた著者は、そこで多くの住民が犠牲になったことを知る。ラバウルに上陸した日本軍は、オーストラリア兵探索と住民統治に当たったが、地元の首長を処刑したり、豪軍の捕虜を銃殺したりした。しかしそれを実行した日本の部隊も、その後、大本営命令で無謀な「ココダの戦い」に送られ、2000㍍級の山々の寒さと飢えのなかでほぼ全滅した。
次のような驚く話も、生還した日本兵から聞くことができた。ラバウルの守備に当たっていた日本軍のズンゲン部隊数百人は、1945年、切り込み隊として豪軍に突撃したものの、死傷者続出でいったん後退した。しかし、ラバウル司令部には「玉砕」の知らせが届いていた。その後傷ついた兵士たちが帰ってくると、司令部は「これでは士気が乱れる」と、指揮官の何人かを無理矢理自決させ、生き残ったその他の兵士はまるで消耗品か口封じのように、再び最前線に送ったという。「もう米軍が日本本土空襲をやっていた時期ですよ。なぜ玉砕する必要があったのか!」
一方、兵士たちを「玉砕命令」で最前線に送り、餓死や病死で二度と日本の土を踏ませないようにしておきながら、命令を出した将校たちは「昼は食堂の銀めし、焼きめし、コーヒー、フルーツパーラーの豪華な食事、夜は宴会と慰安所通いという生活でしたよ」との証言もある。
また著者は、1994年にニューギニア本島の小さな修道院で、日本軍によるティンブンケ虐殺事件を知る。1943年1月、大本営はラバウル防衛のため、14万人の兵隊をニューギニア本島各地に侵攻させた。そこで起こったのがこの事件で、「ティンブンケ村民はスパイだ」との偽情報によって、住民たちの衣服を脱がせて数珠つなぎにし、日本軍の大尉が刀を振るい、また機関銃の一斉射撃によって100人を虐殺した。1994年には遺族が来日して記者会見し、日本政府に謝罪と補償を求めている。
一方、民間人の銃殺を止めようとした軍医がいたこと、大本営の「玉砕命令」下で14万人いた日本兵が、飢えとマラリア、戦病死の果てに1万人に減ってしまったことも記している。
◇ ◇
こうした先の大戦の深刻な経験は、太平洋の島嶼(しょ)国の人々に、独立への力と、大国の経済侵略とたたかう力を与えた。
「世界一の好漁場」といわれるソロモン諸島の海。それは島の奥深くまで広がる原生林に支えられていた。ところがこのソロモン諸島に、戦後は外資の森林伐採企業が殺到し、日本や中国への丸太輸出量が急増した。かつてのガダルカナルの激戦地が、今や生命の丸太を奪いとる激戦地になり、日商岩井、双日、伊藤忠、住友商事などの買い付け業者が動いている。
ソロモン諸島のベララベラ島では、2007年、女性たちが雇われ私兵に素手で立ち向かい、伐採企業を撤退させた。著者はその島に行き、女性たちから話を聞いた。「ブルドーザーの前に何度も横たわった」「ブルドーザーは何度も来た。でも私たちをこえていくことはできなかったのよ」「村の男たちが寝っ転がったら、そうはならなかったわよね!」。身振り手振りで再現する女性たち。みんなで涙を流し、笑い続けたという。ニュースはソロモン諸島中に伝わり、村々に限りない勇気と希望を与えている。
太平洋の島々はまた、戦後は米英仏の核実験場にされ、1980年代には日本の原発の低レベル放射性廃棄物の処分場にされようとした。当時、日本政府は「中川科学技術庁長官(当時)は、放射性廃棄物のドラム缶にキスしても、抱きついても、その横にベッドを置いても大丈夫なほど安全に処理されているといっている」と、バカにした説明をした。岸信介率いるアジア太平洋国会議員連合(私史的な政治団体)は現地に赴き、太平洋諸国の議員代表が提出した「放射性廃棄物海洋投棄反対決議案」を無理矢理廃案にした。
これが現地の人たちの気持ちに火を付けた。当時著者はサイパンにいたが、「サイパンの肝っ玉母さんやおばあさんたちが孫を連れて、よれよれの署名用紙をかき集めて回っている姿は、命がけのなにかであった」と記している。現地の教育庁長官が子どもたちにポスターと作文コンクールを呼びかけ、それを持って代表団が日本にやってきて、高校生のソフィア・ディアスさんが日本の国会議員の前で「海ハ私タチノ母デス。命デス!」と訴える場面は感動的だ。結局、1985年のロンドン条約締約国会議で計画の「無期限凍結」決議が採択された。
戦争でもっとも犠牲をこうむるのは、無抵抗の民間人であり、女性や子どもである。また軍隊の中でも、一銭五厘で召集され戦争の肉弾となった一兵卒である。国境をこえて、そうした弱い者への愛情あふれる一冊。戦後80年の今年、ぜひ手にとってもらいたい。
(三省堂書店/創英社発行、四六判・402ページ、定価2700円+税)





















