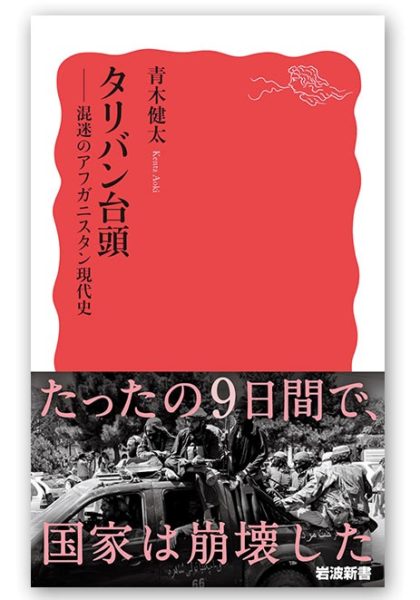
アフガニスタンのタリバンといえば、「恐怖政治」とか「女性の人権の抑圧」というのがメディアが流すイメージの定番だ。米バイデン政権はタリバン政権を認めず、資産凍結の経済制裁を課し、そのため同国内の人々は深刻な飢餓や失業に苦しんでいる。
これに対して、2005年からアフガニスタン政府省庁アドバイザー、在アフガニスタン日本大使館書記官などとして同国で7年間勤務した著者は、「前政権=善、タリバン=悪」という善悪二元論は現実とかけ離れているとして異議を唱えている。同国の歴史的脈絡というバックグラウンドを知ることなしには今を理解できないと、混迷を極めた同国の現代史とそのなかでのタリバン台頭の背景を多面的に明らかにし、現地の正確な情報を求める読者に応えようとしている。
アフガニスタンは、中東、中央アジア、および南西アジアの結節点に位置する国で、19世紀の3度にわたる大英帝国の侵略戦争をはじめとして、常に大国の介入と干渉を受けて翻弄されてきた国だ。アーリア系のパシュトゥーン人が最大民族(人口の4割)だが、イラン系のタジク人、モンゴル系のハザーラ人などがともに暮らす多民族国家で、国民のほとんどがイスラム教を信仰している。近年まで限られた権限しか持たない国王のもと、各部族の内部統治で成り立つ部族社会だった。
タリバンはこのアフガニスタンにおいて根無し草ではない。タリバンが登場した1994年のアフガニスタンは、匪賊(ひぞく)と化したムジャヒディーン各派による内戦が続く無政府状態の只中だった。
ソ連が1979年に同国に侵攻し、これに対して聖戦をたたかうムジャヒディーンにCIAが武器弾薬も資金も訓練も与え、1989年にソ連は撤退した。ところがその後、ムジャヒディーン兵士は匪賊となって暴行、略奪、誘拐、強姦をくり返し、「通行税」と称して市民から金品を巻き上げたりした。血で血を洗う激しい戦闘が続き、多くの国民は難民として隣国に逃れた。
これに対して義憤にかられたイスラム神学校で学ぶ神学生たちがタリバンを結成し、悪事を働く軍閥の成敗に出動するようになった。彼らの多くは戦争のなかで育った子どもたちで、兵士として対ソ戦をたたかった者たちだった。長引く戦乱に辟易していた国民は、タリバンの「世直し運動」に拍手喝采を送り、タリバンは1996年に政権を握った。
しかし2001年のニューヨーク・テロ事件後、アメリカはタリバンがアルカイダを匿っているといって空爆を始め、タリバンは政権を追われた。アメリカは「民主的な国家建設」といったが、できた政権はアフガニスタン人の総意にもとづくものではなく、「臆病で、軽く、使いやすい人物」と見られていたハーミド・カルザイをCIAが推薦し、国連が半ば強制的に彼を暫定政権の首班に指名した。政権中枢を占めたのは、元軍閥のムジャヒディーンたちと、戦禍を逃れ海外に移住していたテクノクラートだった。ブッシュ政権の大統領特使だったハリールザードが同国の閣議に一員として参加するなど、内政干渉も露骨だった。
欧米が押付けた「民主国家」 深刻な汚職も蔓延
著者は、アメリカの後押しでできたこの政権を「砂上の楼閣」と表現している。欧米から巨額の援助が流入したことで、深刻な汚職が政府高官から民間企業やNGOまで隅々に蔓延した。銀行預金を勝手に湾岸諸国の不動産投資に流用する史上最悪の疑獄事件も起きた。米軍による空爆、頻発する民間人への誤爆、夜襲作戦、国民の殺人や拷問、モスクや学校、病院の破壊が増加し、反米意識が高まった。
宗教界や部族長老などの保守層も、外国による急速な近代化に反発した。かつてモスクは、多民族国家でありながら隣人を尊敬しあい、共存しあうコミュニティをつくる機能を果たしていたが、それが民族間の対立が煽られるなかでズタズタに引き裂かれてきたことへの危惧もあったようだ。国民の政治不信がいかに強かったかは、2019年の大統領選の投票率が、史上最低の18・8%だったことにもあらわれている。
だから昨年、アメリカが全米軍を撤退させると発表した後、タリバンが最初に州都ザランジを陥落させてからわずか九日間で全土を掌握したのも必然的だったと著者は見ている。このとき米国製兵器で武装した治安部隊要員は約30万人、一方タリバン兵力は10万人足らずだったが、州知事や国軍司令官はみずから投降した。それは農民はじめアフガニスタンの人々がそれを望んでいたからだ。
「タリバンが女性の人権を抑圧している」という見方に対しても、以下の事実を紹介している。学校は男女別学でなければならない、ヒジャーブを被らなければ外出してはならない――というのはタリバン独自の統治手法ではなく、現地の伝統的な部族社会では、女性の尊厳を守ることが男性の名誉を保つことになるという古くからの考えが根付いており、その表現にほかならない、と。欧米の価値基準にあわない文化や風俗習慣は蔑視し排除するという態度こそ、傲慢きわまりないものだ。
アフガン人主体の発展こそ 干渉でなく支援を
だからといって、著者はタリバンのすべてを肯定しているわけではない。いまや兵力10万を擁する組織は、世直しに立ち上がったメンバーが中核を占めているとはいえ、元ムジャヒディーン各派や様子見で加わった諸勢力もおり、けっして一枚岩ではない。恩赦を与えたにもかかわらず、元政府治安部隊要員を処刑した事実など、さまざまな混乱や否定面も出ているようだ。
しかし注目したいのは、著者が、将来のアフガニスタンはアフガニスタン人が主体となって内発的に発展していくことを基礎にすべきだとのべている点。そして、欧米と立ち位置が異なる日本は、その自助努力の意志を尊重し、介入や干渉ではなく独自の側面支援をおこなうべきだとして、中村医師の事業を例にあげている点だ。
ベトナム戦争の敗北に続くアフガニスタンからの撤退は、「自由、民主主義、法の支配」を掲げて世界各国に内政干渉し、侵略戦争をおこなってきたアメリカの一極支配が終焉し、その地位を急速に低下させていることを示している。本書の内容は現地の実際を知る一助になるし、アメリカ側の情報のみを垂れ流すメディアの犯罪性も浮き彫りになる。
(岩波新書、216㌻、定価840円+税)





















