イズミの30万商圏強奪が背景

リニューアルを計画しているシーモール下関
今秋、下関駅前のショッピングセンター・シーモール下関は創業から40年を迎える。運営母体である下関商業開発(株)は、建物の耐震化と同時に、40周年記念事業としてリニューアル計画を進めてきた。現在、正面入り口や通路には「平成30年3月にリニューアルグランドオープン!! 只今、リニューアルオープンに向けて店舗の移転・改装を行っております。……生まれ変わるシーモールにご期待下さい!」という看板が立っているが、7、8月に飲食店街を中心に退店があいつぎ、惨憺たる状況に直面していることが関係者のなかで話題になっている。ダイエーが撤退し、隣接にはJR西日本関連会社が運営するリピエができ、さらに郊外にはイズミのショッピングモールが包囲する状況のなかで、地元資本が駆逐されていくかのように岐路に立たされている。何が起きているのか見てみた。
店舗撤退相次ぎ空洞化
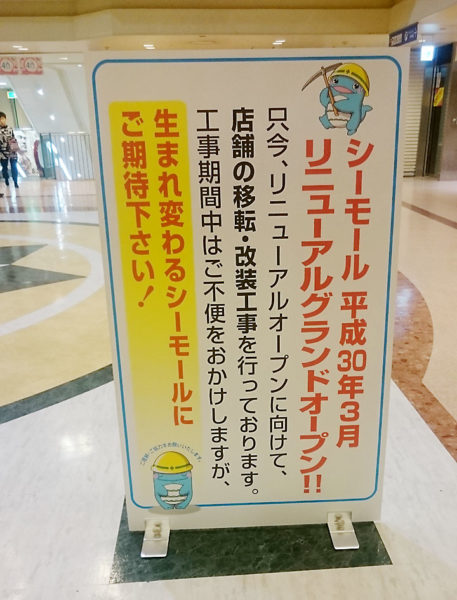
リニューアルを告知する看板
7月から8月にかけて、4階の飲食店街「味の四番街」を中心に閉店が続いた。カフェレストラン、軽食・喫茶、御前屋、とんかつ屋、老舗うどん・そば屋、焼きそば屋など、主立った場所に立地する店がほとんど閉店した。壁になったり、「来年3月オープン」の告知が貼られた空き店舗が並んでおり、ご飯を食べようかと4階に上がってきて驚く客の姿も少なくない。
リニューアル計画をめぐっては、全体構想や日程が不透明であると同時に、地元テナントにとっては多大な投資が必要となり、さらにその後のテナント料が最低で坪1万2000円に値上がりするなどの内容だったため、「やめるテナントが増えるのではないか」と危惧する声が高まってきた。とくに飲食店は調理設備などがある分、店舗を移動するとなると、現在の店舗の解体費用、新規店舗の内容・設備などで数千万円単位が必要になり、地元店舗にとっての負担は大きい。10月末や今年いっぱいで閉店予定の飲食店もあり、既存店で残るのは3軒のみといわれている。飲食店以外でも献血ルームはすでに閉まり、英語教室のNOVAも引き揚げる見込みで、4階はがら空き状態になることが予想されている。
この間に、1階でも地元オーナーがのれんを借りて営業していたサブウェイ(サンドイッチ)が8月末に閉店したり、地下の魚屋が突然辞めてしまったこともテナントに衝撃を与えている。
物販関係を見ると、もっとも人通りの多い2階では、人工地盤に続く通路に展開していた地元大手の雑貨屋オズが撤退し、新たなテナントが入るまで仮店舗で商品を並べているほか、閉店セールを始めた衣料品店あり、閉店が決まったブティックありで、これから閉店が続きそうだ。チェーン系のピンクミックスやクローズアップも本社が撤退の判断を下したようで8月中に閉店した。
ハンドメイドの店や衣類のリサイクル店、ミシン屋など、目立たないながら地道に営業してきた店舗が一つ、また一つとなくなり、「ドコモやハローワークの窓口もいなくなるようだ」「ここも辞めるといっていた」などの話が飛びかうなかで、テナント全体に重たい空気が漂っている。残るか閉店するか最終的な決断を下せない店主もいるため、最終的に今回のリニューアルを経て、「地元勢が20~30軒残ればいい方」という見方が強まっている。
ある関係者は「リニューアルしてグランドオープンというと、普通はもっと前向きな雰囲気だろうが、最近は朝会うと、“お宅はいつまで?”という会話になる。オーナーが一番気をもんでいるだろうが、従業員のなかにも不安が広がっている」と話した。次次退店していくのに、その後に入るテナントがいるのかどうかわからない状況が、みなの不安感に拍車をかけているという。
1977年に開業 下関の豊かさの象徴だったはずが…

1977年のオープン当時

同じ場所の現在
1977(昭和52)年に開業したシーモール下関は、下関大丸、ダイエー下関店を核テナントとして、専門店街には茶山商店街や唐戸商店街などの地元商店220店が入店してスタートした。「ストップ・ザ・小倉」をキャッチフレーズに、大手デベロッパーではなく、地元商業界、経済界が主導して開発を進めたことで、全国でも特異な事例として注目を集めた事業だった。
「下関商業界の命運をかけた大事業」としてシーモール建設計画が始まった背景には、かつて北前船の寄港地として繁栄し、明治・大正・昭和の戦前期には九州や大陸への玄関口として栄えた下関が、戦後その優位性を失い、また李承晩ラインの影響などから水産基地としても衰退の道をたどるなかで、九州圏への経済的流出が顕著になってきたことに対する危機感があった。
さらに、60年代に大都市を席巻したダイエーが、70年代に入って地方都市への進出を始め、流通再編の波が地方都市へと押し寄せようとしていた時代でもあった。全国の商業界がダイエーの出店に戦戦恐恐とした時期で、下関市内では一時は貴船の大津屋跡地(現在のセブンイレブン貴船店)に出店する計画もあったという。そうしたなかで、ダイエーをシーモールの核テナントとして組み込んだうえで、「あくまでも地元商業界が主導し、ダイエー主導ではなかった点は全国でも珍しい形だった」という。
そして、いかに地元商業界を浮揚させるか真剣な議論を重ね、オープン初日には総売上約4億2800万円と予想を上回るスタートを切った。10日間で入店客が100万人を超える盛況ぶりだった。
「♪愛してますか あなた/幸せですか あなた/バラ色の海に つづくまち~//シーモール・シーモール・下関 シーモール・シーモール・下関♪」(シーモール下関の歌)。下関で生まれ育った人人にとっては、テレビのコマーシャルで流れたシーモール下関の懐かしい歌とともに、「知り合いに必ず顔を合わせる場所」として大勢の買い物客で賑わったシーモールの存在は印象強い。屋上の遊園地や時間になると兵隊が出てきて時刻を知らせる仕掛け時計などなど、「シーモールに行く」ことが一種のステータスだった時代を知る地元市民から見ると、「あの豊かさの象徴だったシーモールが…」という思いは強い。
40年の経過を見てみると、20周年の大規模改装のさいに地元商店が大幅に撤退したのに続き、契約更新(10年ごと)のたびに撤退する店舗が出るようになり、地元にかわって大手チェーン店が増えてきたのも特徴だ。2010年にはダイエーも撤退し、以前のような活況は失われてきた。ここ十数年のあいだに急速に消費購買力が減退したことや、イズミがゆめシティやゆめタウンなど郊外型大型店を出店させ、30万商圏に殴り込みをかけてきたことも客足を奪われた大きな要因だ。そんななか、厳しいながらも駅前で40年間継続している地元資本連合によるショッピングセンターは全国でも珍しい。それはチェーンではなく、地元の小売業者が踏ん張ってきたことが大きな要因だと指摘されている。
市が開発したはずが… 150億円投じた駅前「開発」が壊滅へ
今回のリニューアルで、地元店が撤退したあとには、飲食店街に回転寿司が入るとか、3店分の面積を使ってチェーン店が入るといわれており、また3階に大手書店を連れてきてブックカフェをつくる構想、大手スポーツ用品店を引っ張る構想など、さまざまな話が出ては消え、消えては出てをくり返している。今では外資系の大手衣料品店が出店するかどうかが鍵を握っているともいわれている。エスト1階に設置を発表したフードコートに関しても、業者が決まったのかも定かではなく、「5社応募があったが、すぐに断った業者もあったようだ」「数社は決まっているから、一応スタートするだろう」など、さまざまな噂が流れているが、いずれも話題にのぼるのは大手チェーンばかりだ。
「シーモールは地元密着型。屋根付きの商店街のようなもの」と表現する商店主もいる。それぞれの店が顧客を持ち、「今日は元気?」「具合が悪かったら、そこの病院に行ったら」など、1人1人と会話しながら商売してきたという。「わざわざ足を運んで来るのがシーモールで、たまたま行くところがゆめシティ。全国どこにでもあるようなチェーンが入ってきて、はたしてお客さんがわざわざ足を運んでくれるか疑問だ。むしろその独自性・強みに目を向けるべきではないか」と話す商店主もいた。
いまやどこの都市に行っても、どこのショッピングセンターに行っても、同じ味、同じ衣類が並ぶ時代で、まさに金太郎飴状態と化して久しい。下関市内でもイオンやイズミが地元スーパーを駆逐していくなかで、競り負ける流れに拍車がかかった。地元商業の振興をめざして設立した下関商業開発がその志を折り曲げてなお、地元に基盤を置いて独自性を持ったショッピングセンターをつくっていけるのか疑問視されている。ナショナルチェーン重視への転換によって、多くの地元店舗がやむなく行き場を失い、運営する下関商業開発に厳しい視線を向けているのも事実だ。
この間、下関駅前では150億円(55億円を市財政から拠出)をかけた開発がやられ、JR西日本関連会社が運営するリピエなど競合する商業不動産は行政の至れり尽くせりによって増えた。ところが、20~30代の女性たちをターゲットにしていたはずのリピエでも、出店と撤退がくり返され、しまいにはドラッグストアが売り場を占有したり、散散な事態を迎えていることが話題になっている。「下関駅にぎわいプロジェクト」によって開発したはずが、現実には壊滅に向かっており、地方衰退を象徴するようにシーモール下関が空洞化し、混迷していることへの危惧が高まっている。
下関商業開発の筆頭株主である下関市や、運営に口を挟んできた山口銀行など、下関の政財界がどのように関わってきたのか、また今後関わっていくのかが注目されている。





















