ミャンマー国軍は1日、アウンサンスーチー国家顧問兼外相、ウィンミン大統領をはじめ国民民主連盟(NLD)幹部や同党の地方政府トップらを拘束し、立法・行政・司法の全権をミンアウンフライン国軍総司令官が握るクーデターを実行した。これに対してアメリカのバイデン大統領はスーチーらの解放を要求し、国軍幹部への制裁を実施した。ミャンマーを「一帯一路」構想の重要な構成員とみなす中国は、国軍への非難を避け、静観している。一方、ASEAN諸国は内政不干渉の立場に立って事態を注視している。そのなかで、どんな歴史的経過をたどってこうした事態に至ったのか、ミャンマーの人々はなにを考え、なにを望んでいるのかへの関心が高まっている。これについて本紙は、京都大学東南アジア地域研究研究所の中西嘉宏准教授に話を聞き、中西氏の著書『ロヒンギャ危機 「民族浄化」の真相』(中公新書)の紹介と中西氏との質疑応答としてまとめた。
 ミャンマーは東南アジアの西に位置する、人口約5400万人(2020年推計)の国だ。ヒマラヤを源泉とするエーヤワディ川が国土を南北に縦断し、下流のデルタ地帯はコメの一大産地である。
ミャンマーは東南アジアの西に位置する、人口約5400万人(2020年推計)の国だ。ヒマラヤを源泉とするエーヤワディ川が国土を南北に縦断し、下流のデルタ地帯はコメの一大産地である。
民政に移管した2011年以降は「アジア最後のフロンティア」として外国直接投資が急増し、欧米や日本の企業があいついで、中国やベトナムからより賃金の安いミャンマーに拠点を移した。現在、日本や欧米にはアパレル製品を、中国には天然ガスを主に輸出している。
ミャンマーは、ビルマ人が全人口の約6割を占めるとともに、少数民族が100をこえる多民族国家だ。そのうち人口の多いカレン人、カチン人、カヤー人、シャン人、チン人、モン人、ラカイン人にはそれぞれの名を冠した州がある。また、全人口のうち仏教徒が87・9%と圧倒的多数で、キリスト教徒6・2%、ムスリム(イスラム教徒)4・3%、ヒンドゥー教徒0・5%などとなっている。
植民地化と民族的分断 度重なる侵略の歴史
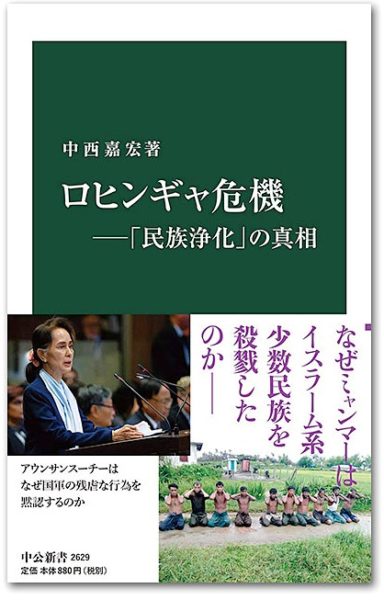
『ロヒンギャ危機』(中西嘉宏・著、中公新書)
ミャンマーの今を理解するためには、ミャンマーがどのような歴史をたどり、どのような国内矛盾を抱えてきたかを知ることが不可欠だ。今年1月に出版された中西氏の『ロヒンギャ危機』にそって見てみたい。
時代は、近代国家もなければ国籍という概念も存在しなかった頃にさかのぼる。1430年にミンソーモン王は、現在のラカイン州北部を中心にムラウー朝を開いた。この王朝は350年以上も続いた。
ムラウー朝は仏教を正統性の原理としたが、非仏教徒やラカイン人以外の民族を排除しない開かれた王朝だった。それは海を通じた貿易と軍事力に支えられていたからで、ベンガル湾を通じてヒトとモノを引き込むことで王朝は繁栄した。16世紀にはベンガル地方から、奴隷として大勢のムスリムをラカインに移住させた。ムスリムの自発的な移住も拒まず、軍人や行政官としても登用した。
19世紀にここに侵攻してきたのがイギリスで、三次にわたる英緬戦争によって現在のミャンマー全体を英領インドの一州にした。このミャンマーのインドへの強引な統合が、後に大きな社会矛盾を引き起こすことになる。
イギリスは、エーヤワディ・デルタ地帯をコメの生産地として開発するために、港湾整備、鉄道敷設、灌漑や運河の造成などに巨額の投資をおこなった。もともと人口が少なかったデルタ地帯に人が集まり、農業労働者の不足をまかなうために中国やインドからの移民も流れ込んだ。
こうして帰属意識や風俗習慣、言語の異なる共同体がモザイク状に共存する社会になった。1920年代には、首都ヤンゴンの人口約20万人の半数がインドからの移民(多くがヒンドゥー教徒)だった。
一方、ラカイン州の北部にはベンガル地方(当時のインド、今のバングラデシュ)から多くの移民(ほとんどがムスリム)が流入した。そしてここでは、仏教徒のラカイン人とムスリムとがそれぞれ分かれて村落コミュニティをつくった。
植民地期のヤンゴンでは、20世紀初頭、ビルマ人による大規模な反インド人暴動が二度起きている。一度はビルマ人港湾労働者がストライキを起こすと、イギリス人経営者がインド人労働者をスト破りに使ったため、ビルマ人が怒ってインド人を襲う事件に発展した。また、インド系や中国系移民の実業家が強い影響力を持ったため、ビルマ人仏教徒はミャンマーの富や女を奪う移民を憎んだという。
当時、宗主国の植民地支配に反対するナショナリズム運動も起こっていたが、それとは別にムスリムを含むインド系移民を敵視する民族的感情がミャンマーの仏教徒のなかに生まれていたことは見逃せない、と中西氏は指摘する。
続いて太平洋戦争開戦直後の1942年、日本軍がミャンマーに侵攻して軍政下においた。このとき、インド系住民約50万人はミャンマーを離れた。
日本軍はイギリスに対抗するため、アウンサン(スーチーの父)を中心とするビルマ独立軍(仏教徒中心)を支援した。一方、イギリスはラカインのムスリムを組織した。仏教徒とムスリムがそれぞれ日本軍と英印軍に動員されたことは、両者の亀裂を深めた。この時期、はじめて仏教徒とムスリムとの大規模な衝突が起きている。
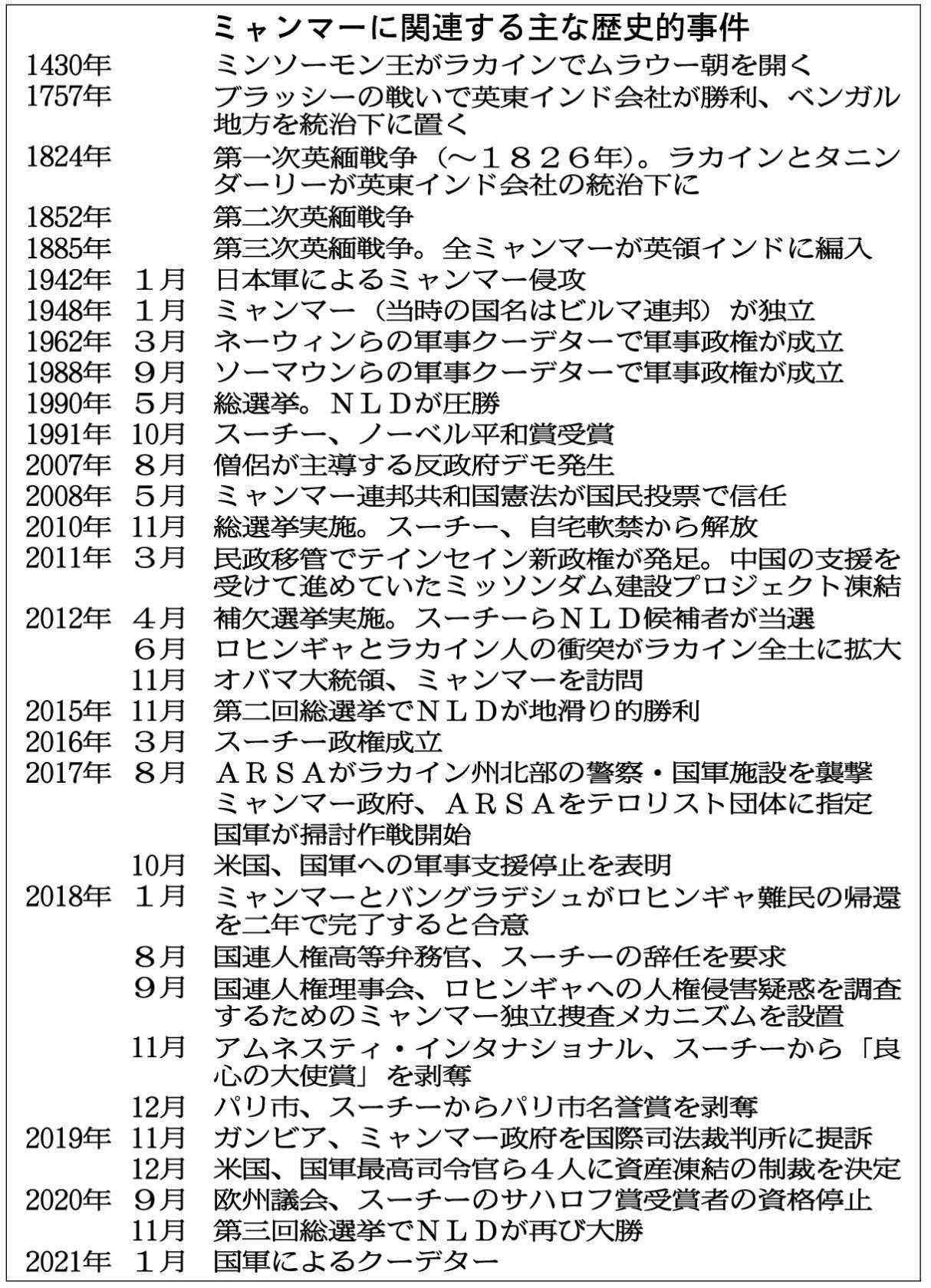
軍政下で少数民族迫害 ロヒンギャは難民に
その後、日本軍が敗戦し、日本軍による名ばかりの独立に不満を募らせたアウンサンらが植民地政府を放逐して、ミャンマーは1948年に独立した。この時期、ロヒンギャという民族名が誕生した。それはラカイン北部に植民地化以前から住んでいたムスリムと、植民地政府による開発で新たに定住したムスリムをひとくくりにしたものだった。民族間の融和が進むかに見えた。
しかし、1962年から2011年まで約50年間続いた軍事政権のもと、人々は独立後に認められた多くの権利と自由を失った。そしてロヒンギャなどの少数民族に対する抑圧は強まった。
まず1962年、国軍最高司令官だったネーウィンがクーデターを起こし、社会主義を標榜する国軍中心の国家をつくり、西側だけでなくソ連や中国にも門戸を閉ざす閉鎖的外交政策を実行した。続いて1988年、同じく国軍最高司令官だったソーマウンがクーデターを起こし、旧世代中心の軍事政権を乗っとって市場経済化を進めた。
統治できない地域を多く抱えたネーウィン政権(仏教徒のビルマ人が多い)は、土着民族中心主義を唱え、1982年に国籍法を決めて、ロヒンギャを土着民族リストから外した。ロヒンギャは国籍を失い、この無国籍状態が今も続いている。
また、バングラデシュ独立戦争によって難民が流入するなか、軍事政権は国籍調査と不法入国者の取り締まり(1978年)や反政府武装勢力の掃討作戦(1991年)をやり、それによってそれぞれ約20万、約25万人のロヒンギャ難民がバングラデシュに逃れた。さらに一九九三年からの「把握・登録・審査」計画によって、ロヒンギャの人口抑制と、ラカイン人やビルマ人のラカイン北部への入植を進めた。
中西氏は、ビルマ人やミャンマー政府に不満を募らせるラカイン人が、同時にロヒンギャをもっとも脅威に感じており、複雑な事態の背景にこの三者の対立があることを理解すべきだとのべている。
民主化が招いた「民族浄化」 背後で糸引く米国

バングラデシュの難民キャンプでビルマ語を学ぶ子どもたち(2019年8月、中西嘉宏氏提供)
では、2011年からの軍事政権が主導した民政移管、民主化によってミャンマーはどう変わったのか?
民政移管の背景には、軍事政権に対して20年以上にわたって制裁で圧力をかけてきたアメリカの存在がある。とくにオバマ政権になると、「アジア回帰」の外交方針のもと、ミャンマーの民政移管を後押しすることで、中国の影響力を抑制する効果を期待した。
アウンサンスーチーが2008年憲法(国軍の高い独立性を保障)を受け入れ、2012年4月の補欠選挙で当選したあとは、スムーズに米国との関係改善が進んだ。同年11月にはオバマが米大統領として初めてミャンマーを訪問し、実質的にすべての制裁を解除した。2015年の総選挙ではNLDが改選議席の3分の2を獲得し、翌年3月にはスーチー政権が誕生した。
しかし中西氏によれば、この民主化そのものが、ラカイン州とミャンマーの国民国家形成の歴史を下地としつつ、仏教徒とムスリムとの暴力的衝突の引き金になった。なぜなら、民主主義の原則である多数決主義は、主要民族(ここではビルマ族)を代表する人々に国家権力を握る機会を与えやすく、そうなると最悪の場合、少数民族の排除(民族浄化)が起きるからだ。
スーチー自身もそこから自由ではなかった。スーチーはロヒンギャへの迫害に対して、「彼らは本当のビルマ人ではない。彼らはバングラデシュ人よ」といっている。2012年の総選挙で、NLDの1000人をこす候補者のなかに、ムスリムは一人もいなかった。
そしてスーチー政権のもとで最悪の事態は起きた。きっかけは2012年、ラカイン州(ラカイン人64・6%、ロヒンギャ31%)で起きた、ラカイン人女性(仏教徒)に対するロヒンギャ男性(ムスリム)の集団暴行事件で、翌年には仏教徒とムスリムの衝突は全土に広がった。ラカイン州以外では、仏教徒によるごく少数のムスリムへの一方的な攻撃となった。仏教のカリスマ僧侶たちの反イスラーム的扇動が大きな役割を果たした。
2017年8月25日未明、ラカイン州北部で、ロヒンギャの武装集団=アラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA)が国境警察と国軍施設を襲撃した。これには地元住民が多数動員されており、長年蓄積した不満から手近な農具を持って政府に立ち向かう民衆蜂起の側面があった。
ミャンマー政府は即座にARSAをテロリスト団体に指定し、国軍が掃討作戦を開始した。このテロ指定が民衆蜂起の側面を見えなくした。国軍はARSAの戦闘員と村人を区別しなかった。せいぜい数百のメンバーを、国軍が1万人とみなしたのはそのためだ。掃討作戦は逃げ惑う民間人の無差別大量虐殺や村の焼き払いとなった。数千人以上が殺され、約70万人のロヒンギャ難民が隣国バングラデシュに流出した。現在も100万人の難民が困難な生活条件の下で暮らしている。
2019年末には、国際司法裁判所に、西アフリカのガンビア政府がジェノサイド条約違反でミャンマー政府を提訴した。スーチー政権と国軍はジェノサイドを認めていない。ただ、スーチーはその後、国軍による残虐行為を認めるようになった。
この事態を解決するために中西氏は、欧米や国連のような強硬手段ではなく、現地社会の安定を生むための現実的な関与が必要だとのべている。ミャンマーは破綻国家ではなく、自身の意志に反する外部からの関与を拒絶する意志と能力があること。ミャンマーは民主化途上の国であり、文民政権の権限には限界があること。国連人権理事会が設置した独立国際事実解明ミッション(IIFFM)が提言するような、司法を通じた処罰やミャンマーへの制裁を求める圧力は、効果を生まないどころか、国内の諸勢力の反発を生み、人権状況の悪化につながりかねないこと、などを踏まえたうえで、日本はロヒンギャ難民の帰還とミャンマー国民としての受容をミャンマー政府に促す(人道支援などを通じて)という役割をはたすべきではないかとのべている。
中西氏は何度もミャンマーを訪れ、ヤンゴン大学の客員教授として学生たちと語り合った経験を持つ。中西氏は「あとがき」で、今のミャンマーの状況は単純な善悪の構図だけでは理解できないし、それでは解決の糸口は見えてこない。過去と現在を広く検証し、問題の根深さや複雑さを知ってほしいとのべている。
■中西氏との一問一答
本紙は2月1日に起こったミャンマーのクーデターについて、いくつかの点を中西氏に聞いた。
Q 今回のクーデターの原因をどう見るか?

中西嘉宏・京都大学准教授
A 昨年の総選挙で不正があったという主張は、野党と国軍からあがっている。とくに国軍は有権者名簿の不備について独自の調査結果を公開するなどしてきた。まったく不正がなかったとは思わないが、選挙の不正を防ぐための手段が講じられており、選挙監視もおこなわれている。選挙前の予想でもNLDが有利といわれていた。選挙結果の大勢をくつがえすような不正はなかったと見ている。
ただ、そうした不正疑惑の追及について、アウンサンスーチー政権はまともにとりあわなかった。この態度が国軍の威信を傷つけたことは間違いない。それにより、ずっと敵対関係にありながら同じ政権で共存していた両者の亀裂が決定的になった。そしてクーデターへとつながったと考えている。
Q 「スーチーを解放せよ」とのデモが連日起こっていると報道されている。スーチーはミャンマーの中のどういう層が支持しているか? アメリカはスーチーを外交上の重要な駒としているようだが、スーチーは米国政府にどういう態度をとっているか?
A スーチーに対する支持はエリート、中間層、庶民各層に広がっている。見るかぎり、とくに庶民層の支持はスーチーへの信奉に近いものがある。アウンサン将軍の娘ということもあるが、1988年から2011年まで続けてきた長年の軍事政権に対する抵抗が支持につながっている。イギリス人の夫がいることにこだわる層は保守層や民族主義的な傾向を持つ人たちにわずかにいるようだが、かなり少数だ。
スーチーと米国政府との関係は、かつてはとくに米国議会の有力議員が民主主義のシンボルとしてスーチーを支援していた。ところが、2017年にロヒンギャ難民流出が起きて以降は、両者の距離は空いたといえる。実質的な国家指導者となったことでスーチーもかつてほど国際的な支援を必要としなくなった。
Q 民政移管当時、新大統領テインセインの大統領顧問になった人々はスーチーらと一線を画して現実的な改革をめざした第三勢力(知識人や実業家)だったというが、現在その勢力はどういう態度をとっているか?
A 第三勢力の多くはスーチー政権の登場で政権の外に出た。そして一部の人は今の軍政によって登用されている。しかし、もはや重要な役割は果たしていない。私の知る限りでは、スーチーを批判する人たちと、代わるリーダーがいないという理由で消極的にスーチーを支持する人に分かれていたように思う。
Q 50年間権力を握ってきた国軍の実態はどうか? また国軍と中国との関係は?
A 国軍系の企業や国軍の高級将校たちが各種の利権を握っていることはよくいわれている。国軍にとって中国は潜在的脅威なので、友好関係を保ちつつも警戒するというスタンスをとっている。国軍が中国の傀儡ということは絶対にない。彼らはナショナリストの集団だ。外部からの介入を嫌うので、その分、内政不干渉を原則とする中国と付き合いやすい面はあるだろう。
Q 「開発途上国であるミャンマーの中でもラカイン州は最貧困地域で、トイレ設備のない世帯が46%」「ラカイン州の紛争の背景には貧困がある」と書いてあったが、民主化後の日本を含む先進国の経済進出で現地の経済格差が拡大した面はあるか?
A 経済格差はもともと大きい。その格差は2011年の民政移管後には統計的には縮小している。インフラを見ても農村部の電化率が上がるなど、経済発展の果実が地方にも届き始めている。とはいっても、都市と地方、所得階層上の格差は大きい。とくにラカインのような紛争が起きている地域には民間資本の進出が遅れてしまい、経済発展からとり残される傾向にある。格差の是正には、経済発展の持続と政府による再配分の充実が必要だ。今回のクーデターは、その両方にとってマイナスの影響があると考えられる。
Q 現在アメリカは経済制裁を強める方向だが、ミャンマーの側に国際社会への不信感がある以上、それは逆効果にならないか?
A 経済制裁によって、今回の非常事態宣言を受け入れないという姿勢を示すことは外交的に重要だ。ミャンマー国軍は、制裁があろうがなかろうが、アメリカに耳を貸すことはない。ただ、どちらかというと制裁の方が、市民にばかり被害が及ぶ可能性がある。逆効果というよりも、狙った効果を上げられないということだ。日本のメディアからは、「スーチーを救え」だけではなく、日本外交の強みを活かして国軍の説得をという議論も聞かれる。働きかけは必要と思うが、国軍は外国の要求を聞くような組織ではない。外交にできることに限界があることは認識しておいた方がいいだろう。
Q 歴史的に見て、先進国の側のミャンマーへの介入が不幸を生んできたと感じる。今の局面で、日本人としてなにができるか?
A デモ隊が多くの英語のプラカードを持っているのは、国際社会に対するメッセージだ。すぐに日本人ができることはないが、クーデターに抵抗しているミャンマーの市民が一番恐れているのは、世界から忘れられることだ。彼ら、彼女らを支持するのであれば、これからミャンマーに関する報道が減ってきたとしても、関心を持ち続けることが必要なのではないか。





















