
イスラエルの攻撃によって廃墟と化したガザ。4カ月以上続く攻撃によるパレスチナ人の死者は3万人をこえている。
京都大学で13日、自由と平和のための京大有志の会などの主催による公開セミナー「人文学の死――ガザのジェノサイドと近代500年のヨーロッパの植民地主義」が開催された。昨年10月7日から始まったパレスチナ・ガザ地区に対するイスラエルの破壊と殺戮が苛烈さを増すなか、人文学の視点からこの暴力の歴史的根源に迫った。オンラインも含め約600人が参加した。今号では、岡真理・早稲田大学文学学術院教授による基調講演「ヨーロッパ問題としてのパレスチナ問題」の内容を紹介する。
◇ ◇

岡真理氏
本セミナーは、この4カ月間、今なおガザで生起している出来事――イスラエルによるジェノサイド(大量殺戮)、ドミサイド(大量破壊)を、この暴力の根源に遡って理解することを企図している。
昨年10月7日、ガザ地区――マスメディアでは「イスラム組織ハマス」あるいは「イスラム原理主義組織ハマス」が実効支配するガザ地区と説明されるが、ガザ地区は1967年以来、イスラエルの軍事占領下にあり、2007年から16年以上にわたってイスラエルによる軍事封鎖の下に置かれている、そのガザ地区――のパレスチナ人コマンド(戦闘員)によるイスラエル領内への越境奇襲攻撃があり、直後からイスラエルによるガザに対する凄まじい攻撃が始まった。
開始からわずか1週間後、ジェノサイド研究の専門家が「教科書に載せるような」、すなわち絵に描いたような典型的なジェノサイドだと述べ、第二次世界大戦後、カンボジアのキリングフィールドをはじめ数々のジェノサイドを体験してきた国連の専門家も「前代未聞」と述べるほどの異次元のガザに対するジェノサイド攻撃だが、日本の主流メディア、企業メディアの報道は、パレスチナ系アメリカ人の文学研究者エドワード・サイードが批判する「カヴァリング・イスラーム」、つまり中東やイスラーム世界で起きる出来事を報道することを通じて、むしろ積極的にその内実や本質を覆い隠してしまうという事例をそのまま体現したものとなっている。
典型的なのは、「憎しみの連鎖」とか「暴力の連鎖」という言葉への還元。これはこの問題の起源――イスラエルの暴力の歴史的起源を問わないで済ませるための詐術だ。また「イスラエルとパレスチナ紛争には複雑な、非常に入り組んだ歴史がある」といってお茶を濁すことも、同じく歴史について語らないための方便である。
イスラエルによる「我々はホロコーストの犠牲者であるユダヤ人…」という主張も、イスラエル国家においてホロコーストの記憶が歴史的にどのように政治的に利用されてきたかということについて無知なまま、イスラエルが主張するがままに流布され、あまつさえ2000年前に遡って、歴史的事実としては存在しない「ユダヤ人のパレスチナ追放」なるものを紛争の歴史として説明するという、度しがたい無知に基づく報道がなされている。
文庫版で600㌻にわたるシュロモー・サンドの著作『ユダヤ人の起源』を読んでから報道せよとまでは言わないが、ウィキペディアにさえ「4世紀までパレスチナ住民のマジョリティー(多数派)はユダヤ教徒であった」と載っている。
そして、ローマ帝国がキリスト教を国教とし、キリスト教への改宗者が増え、キリスト教徒が多数派となり、さらにアラブ・イスラームに征服された後、ユダヤ教徒やキリスト教徒のイスラームへの改宗が進み10世紀を過ぎたあたりからムスリムが多数を占めるようになるが、歴史を通じてパレスチナにはユダヤ教徒がずっと存在した。エルサレムへの入場は禁じられたかもしれないが、パレスチナからユダヤ人住民すべてが追放されたという事実はない。このような初歩的な事実確認さえ怠ってテレビや新聞の報道がなされている。
今の日本人の多くが、仏教徒であろうが、キリスト教徒であろうが、ムスリムであろうが、2000年前にこの列島に居住していた縄文人の末裔であるように、あるいはその後朝鮮半島からやってきた渡来人の末裔であるように、パレスチナ人は2000年前、パレスチナの地にいたユダヤ教徒の末裔である。
攻撃開始から4カ月 問題の根源にこそ目を

イスラエルの爆撃で壊滅したガザ地区南部ハーン・ユーニスの市街地(12日)
今、ガザで生起しているのはジェノサイドにほかならない。攻撃開始から129日目の現在、イスラエルの攻撃によるパレスチナ人の死者は、2万8340人を超える。これは身元が判明している者たちだ。行方不明者、すなわち遺体がまだ瓦礫の下に埋まっている者たちは約8000人。実質の死者は3万5000人を超えている。負傷者は6万7984人。これら死傷者の40%が14歳以下の子どもたちだ。
230万人いるガザ住民の80%にあたる190万人が家を追われ、北部を追われ、さらに中部を追われた避難民たちが今、エジプト国境の街ラファに追い詰められ、飢餓や感染症で命を落としている。このいわば「攻撃関連死」による死者たちは、先ほどの数には計上されていない。ガザの住宅の60%が完全に瓦礫にされてしまったか、損傷を受けた。現段階で60万人がもはや帰る家がない。
今、ガザで起きていること――それは人間存在をめぐって私たちが培ってきたあらゆる普遍的価値観に反するものだ。それを否定し、蹂躙するものだ。このジェノサイドを私たちは一刻も早くやめさせなければならない。そのために声を上げなければならない。
しかし問題は、ジェノサイドそのものではない。問題の本質は、ジェノサイドにあるのではない。本セミナーは、それを提起し、広く共有し、私たちの行動の指針にするために企画された。
今、日本の各地で「今こそ停戦を」「ジェノサイドやめろ」と呼びかけるデモがおこなわれている。京都でも毎週土曜午後3時から市役所前に集まって仏光寺公園までデモをおこなっている。都道府県や市町村議会で即時停戦を求める決議がなされ、さまざまな団体が即時停戦のため日本政府に対して「憲法前文の理念に則り、積極的な措置をとれ」と求める声明を発表している。
毎日、100数十人から200人近いパレスチナ人がガザで殺されている。10分に1人、子どもが殺されているとも言われている。一刻も早くこのジェノサイドをやめさせなければいけない。それは事実だ。そうしたなか、今すぐ停戦を求め、声を上げている方のなかには「ハマースのテロは許されないけれど、それにしてもイスラエルの行為はあまりに過剰だ」「ジェノサイドだ」「ことの発端はどうあれ、こんなことはすぐに止めなければならない」という思いで参加されている方も多いのではないかと思う。
一刻も早く止めるために、理由はどうあれ即時停戦を求める声を今、糾合していかなければならない。しかし、このジェノサイド攻撃が終わったとしても、問題の根源が解決されない限り、パレスチナの地に平和は訪れない。即時停戦、ジェノサイドをやめろと叫びながら、私たちは何を願っているのだろうか。何を実現しようとしているのだろうか。
彼の地で起きているジェノサイドが終わりさえすればいいのだろうか?そうではないはずだ。私たちが願い、そのために今できる限りのことをしたいと思っているのは、パレスチナが平和になること、パレスチナの地に暮らす人々が自分の人生と自分たちのあり方をみずから決定し、人間らしく、自由に、平等に、尊厳をもって生きていることができるようになることではないか。
そうであれば、単にジェノサイドが終わるだけでは不十分だ。問題の根源にこそ、目を向けなければならない。
イスラエルの建国 民族浄化と殺戮の上に

ガザの住民を南部に追いやりながら軍事侵攻を続けるイスラエル軍(9日)
では、この暴力の起源、問題の本質とは何か。それを考えるにあたって踏まえておかなければならない基本的なポイントとして、イスラエル国家は入植者による植民地主義的侵略によって先住民を民族浄化することによって建国されたという歴史的事実がある。すなわちアメリカやカナダ、オーストラリア、あるいは南アフリカの白人国家と同じ存在であるということだ。
そして、イスラエルは自身が支配する全領域――すなわち1948年に占領し、現在イスラエルと呼ばれている地域、および1967年に占領した東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区およびガザ地区において、ユダヤ人至上主義のアパルトヘイト体制を敷いているという事実だ。それゆえ今起きていることは植民地戦争であるという事実である。
昨年10月7日のハマース主導のガザのパレスチナ人コマンドによるイスラエル攻撃は、脱植民地化を求める者たちの抵抗と位置づけられる。パレスチナ系アメリカ人の歴史学者ラシード・ハーリディー(コロンビア大学教授)は、10月7日直後の講演会において二つのことを強調した。
一つは、歴史的な脱植民地化を求める解放軍も暴力を行使してきたこと。アルジェリアやアイルランド、ベトナムの民族解放闘争も然りだ。
もう一つは、この植民地戦争においては、戦闘がおこなわれている戦場だけでなく、世界のメトロポール(大都市)もまた戦場であるということだ。それは、イスラエルが攻撃直後におこなったことだ。
つまり、10月7日に起きたことについて、ないこともでっち上げて世界に向けて喧伝する。10月7日の奇襲において、パレスチナの戦闘員たちは軍事的には勝利したかもしれないが、世界の大都市を舞台にして展開されるこの情報戦においては、イスラエル政府の発表が検証もされず事実であるかのごとく共有され、その後の議論も「ハマースによる残忍なテロ云々」を前提にしなければ次に進めないという言論状況が生まれた。
私たちは、ガザのジェノサイド、ドミサイドという形で現象している暴力を、正しく適切に理解する――つまり問題を根源的に解決する“解”を導き出す――ためには、以下のことをしっかりと理解しなければならない。
今、ガザで起きていることは、入植者植民地主義によって建国され、ユダヤ人至上主義体制を維持するためにアパルトヘイトを敷いている国家に対して、先住民がそれからの解放を求めて戦っている脱植民地化の戦いであり、植民地戦争であるということ。
そして、イスラエルがガザのパレスチナ人に対して行使している暴力は、日本も含めて世界の植民地主義国家がその植民地支配の歴史において、自由や独立を求める被植民者の抵抗に対して行使してきた殲滅の暴力であるということ。
また、ガザに対するジェノサイドと並行して、ヨルダン川西岸地区に対しても今、第二次インティファーダの時期を上回る規模の攻撃が起きている。これも、イスラエル国家とそのナショナルイデオロギーであるシオニズムそのものの企図――ヨルダン川から地中海までの土地を占有し、パレスチナ人を民族浄化する――という目的を遂行しているのだということ。
このような文脈において、今の暴力を理解しなければならない。
イスラエル政府の発表、アメリカの主流メディアの報道、そして日本のメディアの報道は、ひとえにこのジェノサイドが植民地主義の暴力なのだという事実を徹底的に抑圧、隠蔽するためのものとして機能している。
イスラエル政府は10月7日以降のガザに対するジェノサイドを正当化するために、「10月7日にハマスが赤ん坊数十人の首を切り落とした」とか、「オーブンで焼き殺した」とか、「野外音楽祭で大量レイプがあったのだ」というが、これらはすべてでっち上げの嘘であったことが、すでにイスラエルの新聞でも報道されている。だが、このでっち上げによって「ハマースの残忍なテロ」という虚偽が世界に喧伝された。
パレスチナ側の戦闘員の攻撃で民間人が殺されていないわけではない。そうした戦争犯罪は確かに起きている。だが、それはイスラエル政府が発表している内容とは大きく異なるものだ。そして今、当初1400人といわれていたイスラエル側の犠牲者が1147人に下方修正されているが、そこで犠牲になったイスラエル市民が、誰によって、どのように殺されたのかということについてイスラエル政府は調査して発表することを拒んでいる。
すでに証言等で明らかになっているが、現場に急行したイスラエル治安部隊が人質や自国兵士もろとも砲撃したり、アパッチヘリから発射したヘルファイアミサイルによって車ごと破壊され殺されたりすることによって、かなりのユダヤ系市民が自軍の攻撃によって殺されている。
10月7日のパレスチナ側の攻撃があったことを契機にイスラエルのユダヤ系市民が殺されたことは事実だが、すべて「ハマースが残忍なやり方で殺した」というのは間違いであり、パレスチナ側の戦闘員が殺した実数もイスラエル政府が明らかにしようとしないためはっきりとはわかっていないのが現状だ。
こうした虚偽を流しながら、イスラエルは「このテロに対する自衛の戦いだ」と喧伝しているが、これは実際には1948年以来やむことなく今日まで継続するパレスチナの民族浄化――漸進的ジェノサイド――の完遂にほかならない。
詳しくは『現代思想』2月号のパレスチナ特集を読んでもらいたい。これが私個人の見解ではなく、パレスチナ・中東研究に携わる者たちの基本認識であることがご理解いただけるだろう。
何の為の研究教育か 問われる人文学の真価
「ナチスのホロコーストを前にして、人間になぜこんな残虐なことができるのか、と問うのは偽善的である」と、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンは述べた。「私たちが問うべきはむしろ、それは一体いかなるシステムによって可能になったのかということである」と。本セミナーで考えたいのは、まさしくこのことである。
「システム」という言葉で真っ先に想起されるのは、国連の安保理常任理事国であるアメリカが拒否権を持っているということ。そのためにイスラエルは、その数々の国際法違反も戦争犯罪も人道に対する罪も、一度も裁かれることはなかった。この「イスラエル不処罰」という国際社会の「伝統」が21世紀の今、ジェノサイドを可能にしてしまったということは否めない。80年前の戦争の戦勝国がこのような形で拒否権を持ち、それゆえに世界の大半の国々の意向をチャラにすることができるという構造自体が、不正義の温床になっているということは、誰の目にも明らかだ。
本セミナーでは、ガザに対するジェノサイドを何が可能にしてしまっているのかということを、そのような国際政治の観点からではなく、私自身が専門とする「人文学の学知」という領域で考え、問題提起することを目的にしている。
封鎖されたガザに対するイスラエルの大規模軍事攻撃は過去に4回あった。2008年から09年にかけての最初の攻撃、3回目の2014年の「51日間戦争」では、私もパレスチナに関わる者の一人として、ガザで一方的な殺戮と破壊が起きているということを知らしめるために各地で話をしたり、情報発信したりしてきたが、今回、開始から時を置かず、それが過去の攻撃とは異次元のジェノサイド攻撃であるという事態を前にして、私の中にあったのは、人文学に携わる者として私自身が問われている、という意識だった。
アラビア語の授業でも、文学の授業でも、今ガザで起きていることが何を意味しているのかという、その人文学的意味を語らずにはおられなかった。アラビア語の授業だから、または中東文学の授業だから、アラブ・中東世界の一部であるところのパレスチナで今起きていることについて語る、というのではなく、なぜ大学で英語以外の言語を学ぶことが必修とされているのか、なぜ文学が世界に存在し、私たちがそれを学ぶことに価値が置かれているのか、その「人文学」というものの意味を踏まえたとき、今ガザ、パレスチナで起きていることを人文学的観点から伝えなければならない。そのことの意味を語らなければならない。そうでなければ私自身がこの先、何を書こうが、何を語ろうが、そんな人間の言葉は信用できない。文学を通して教育や研究をしているヒューマニティーを自分自身が裏切ることになるという切迫した危機意識だった。
どの言語のどの国の文学であれ、どの国の歴史であれ、哲学であれ、人文学(ヒューマニティーズ)に関わるとは、その専門とする地域や言語をこえて、そういうことであると思う。
「関心領域」の外側で 現在も続く植民地主義
2021年6月、私は名古屋の入管で強制収容中に亡くなったウィシュマ・サンダマリさんの告別式に参加した。私たちの社会が殺した――その意味で私もまたその死に対して責任を負っている――ウィシュマさんの姿を自分自身の記憶に焼き付けるためだ。ヨーロッパにおけるユダヤ人の死と、ウィシュマさんの死はつながっている。
ナチス・ドイツの時代において、ナチス支配地域では「ユダヤ人」というラベリングは、そのように呼ばれた者たちに対して何をしてもよいということを意味した。100年前の日本でのそれは「朝鮮人」だった。誰かを「朝鮮人」と呼びさえすれば、それは殺しのライセンスとなった。2001年9月11日以降、それは「テロリスト」だった。アメリカのグァンタナモ収容所では「テロリスト」の嫌疑をかけられた者たちが、国際法も国内法も適用されない法外な場に置かれた。
今ガザに関して、それは「ハマース」だ。「ハマースが…」と言いさえすれば、パレスチナ人に対して何をしてもいい。そして今、日本では非正規滞在の外国人がそれにあたる。ジョルジョ・アガンベンがいうところの「剥き出しの生」に還元された者たちだ。
私にとって人文学とは、歴史や世界を見るこのような視座を与えてくれるものだ。私たちが歴史や文学、哲学や人類学、その他の人文学を学ぶのは、私たちがそのようなパースペクティブでこの世界の歴史と世界を見るためだ。
参政権を持つ日本国家の構成員である私は、イスラエルによるガザのジェノサイドと、その陰でヨルダン川西岸地区で進行する凄まじい民族浄化の暴力について批判するとき、この日本という国が植民地戦争において中国で、朝鮮で、台湾で脱植民地化のために戦う者たちを凄まじい暴力で殲滅してきたということに対する批判なしに、あるいは植民地支配のための被植民者の監視管理に起源を持つ入管法によって今、非正規滞在者が人権の番外地に置かれ、毎年のように入管の収容施設で亡くなっている事実を批判することなく、イスラエルを批判することはできない。
第二次世界大戦中のドレスデン爆撃を上回ると言われるガザに対する爆撃を前に日本人が想起するのが、ゲルニカや広島・長崎、あるいは東京大空襲だけであったなら、私たちはこれを批判する資格を持たない。広島・長崎に対する原爆による大量殺戮、一晩で広島の1945年12月末までの被爆死に匹敵する市民を殺した東京大空襲に先立ち、日本が敗戦まで中国・重慶に対する戦略的都市爆撃をおこなっていたという事実が想起されなければならないはずだ。すべてはつながっているのだ。
しかし、私たちはそれを歴史の授業で学んでいるだろうか。「植民地主義」という言葉も、日本がかつて台湾や朝鮮を植民地支配したということも、確かに歴史の授業で学ぶが、それは単なる「言葉」に過ぎないのではないか。植民地支配の暴力が、支配される者たちにとっていかなる暴力であったのかということを私たちは学んでいるだろうか。ゲルニカは知っていても、重慶の爆撃について知っているだろうか。
10月7日のパレスチナ側の攻撃における民間人の殺害や拉致ということが語られるが、パレスチナを民族浄化して難民となった者たちをガザに閉じ込め、彼らが住んでいた村を破壊して、その跡地につくったキブツ(生活共同体)――その内実はガザに対するイスラエル軍の地上攻撃にさいして前哨基地として使われる準軍事施設であり、住民の男たちは軍事訓練を受け武装し、いつでも電話一本で一時間後には予備役として戦闘に携わるという前提で生活している――の植民者を、戦闘員と区別される民間人と見なすことを無条件に受け入れるということに対して、たとえばかつて満洲に入植した日本人が満洲で果たした侵略的役割を考えるならば、私は倫理的な躊躇を覚えざるを得ない。
すべてがつながっているのだという「知」を与えてくれるのが人文学であり、大学で人文学の研究・教育に携わるということは、そのような知を、世界をまなざすそのような歴史的、今日的視座を、若者たちに養うということだと私は考える。こうした歴史的視座なくして、アジアの平和も、世界の平和もない。
ガザのジェノサイドは、パレスチナや中東を専門とする研究者だけの問題ではない。アメリカ研究や国際政治の専門家だけの問題でもない。
岩波書店『世界』新年号で駒込武さんが台湾とパレスチナをつなげた論文を書かれたが、そのような視座を提示していただいたからこそ、私も同じ号に寄せた論考で、日本の台湾支配がなければ「霧社事件」がないように、イスラエルの占領・封鎖がなければ10月7日のハマース主導の攻撃もないし、そもそもハマース自体が存在しないのだという趣旨のことを書いた。
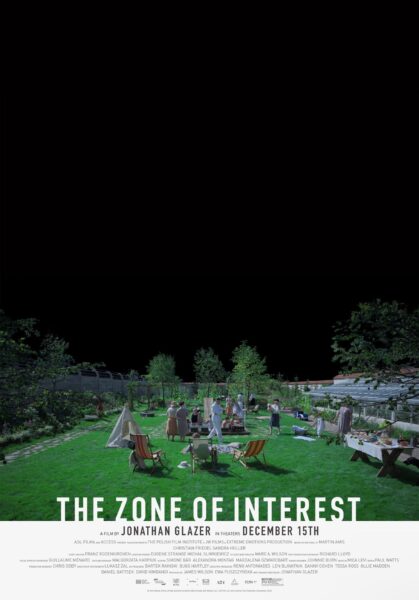
映画『関心領域』(ジョナサン・グレーザー監督)
逆にいえば、日本の人文学に携わるマジョリティーにとって、ガザで今、起きていることが、自身の「関心領域」とあくまでも接続されないままであるならば、それは人文学者自身がみずからの学問に死を宣告しているに等しいということだ。
「関心領域」とは、今年5月下旬に日本でも公開が予定されている映画の題名だ。カンヌ映画祭でグランプリを受賞し、アカデミー賞作品賞候補にノミネートされている。アウシュヴィッツ強制収容所と壁一枚隔てた屋敷で暮らしている所長一家の物語である。
同じように、ガザのジェノサイドが進行している今、私たちはスマホの画面越しに毎日それを目撃し、認識している。だがこの地では、それとは全く別の平和で安らかな生活がある。あの当時、アウシュヴィッツの大量殺戮によって犠牲になった者たちの財産や金歯、頭髪その他が資源として活用されていたように、たとえば東京五輪では占領下のパレスチナ人の人権剥奪と抑圧の上に蓄積されたイスラエルのセキュリティー技術が活用された。
伊藤忠と日本エヤークラフト社のイスラエル軍事企業エルビット・システムズ社との契約が、この間、市民の皆さんが声を上げ、活動することによって停止に追い込まれたが、これまでは、そうしたビジネスによって日本企業が収益を上げ、その恩恵に日本社会に生きる私たちが少なからず与っていたということになる。
強制収容所で被収容者たちが置かれた――プリーモ・レーヴィの言葉を借りれば「これが人間か」というような――状況と、壁一枚を隔て、あたかもそんな現実など存在しないかのように安楽と人権を享受する者たち。この「関心領域」という映画におけるドイツ人家族と、ガザのジェノサイドを「遠い中東の話」であると見なす者たちとをどうしても重ねて考えないわけにはいかない。
さらに敷衍(ふえん)して考えれば、これはかつて植民地支配をしていた時代、さらに現在における世界的な奴隷制システムのもとで、それは比喩的に「壁一枚」しか隔たっていない向こう側で起きていること、見たくない事実を見ないことによって安全と平和と物質的豊かさと人権を享受している、このグローバルノースの中産階級以上の者たちの暗喩であると思う。
それはまた、イスラエルのユダヤ人にとっては、壁一枚、フェンス一枚隔てた向こうのガザ地区で、76年前に自分たちが民族浄化をして追い込んだ者たちが16年以上続く封鎖の中で「これは生きながらの死だ」というような生を強いられ、10月7日以降は4カ月で1万人以上の子どもたちが殺され、完全封鎖によってラファでは飢餓と感染症で人が命を落としている、まさに「絶滅収容所」を彷彿とさせる状況にあるという、見たくも知りたくもない現実に目を向けることなく、自由で民主的な生活を享受しているということの暗喩ではないか。
パレスチナ問題 その起源はどこにあるのか
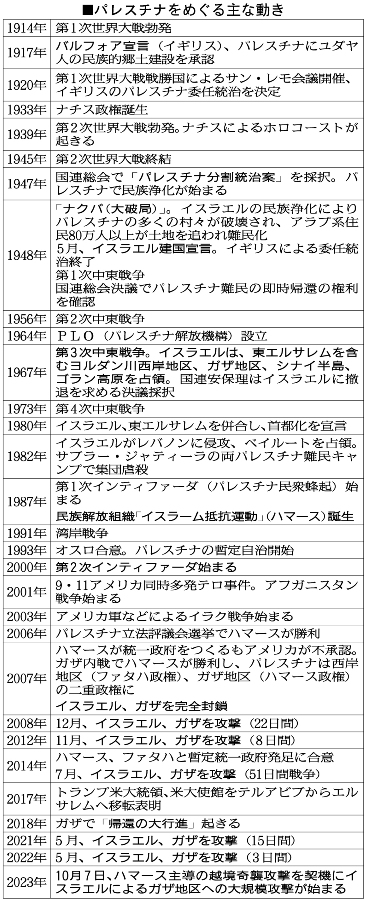
今、ガザのジェノサイドという形で生起している暴力は、パレスチナ問題といわれる問題の現象的なあらわれの一つだ。パレスチナ問題の起源とは、先述したように1948年にパレスチナに「ユダヤ人国家」を標榜するイスラエルが、パレスチナ人を民族浄化する形で建国されたことにある。この難民化と故国喪失をアラビア語で「ナクバ(大破局)」という。
では、なぜパレスチナにユダヤ国家を作ることになったのか? それは19世紀末にパレスチナにユダヤ国家をつくるという運動――政治的シオニズム――がヨーロッパで誕生したからだ。それはなぜか? 反ユダヤ主義があったからだ。
反ユダヤ主義とは何か? 英語では、Antisemitism(反セム主義)という。「ユダヤ教徒は、ヨーロッパ・アラビア人種ではなく、中東にいるアラブ人と同じセム人なのだ」とする人種主義だ。ヨーロッパ人というのはキリスト教徒のことであって、ユダヤ教を信仰する者たちはセム人種だという。そもそも「人種」という概念そのものが似非科学であり、さらに「セム人」などというカテゴリーは存在しない。19世紀においてユダヤ教徒を別人種と見なすこと自体がレイシズムだ。
では、ヨーロッパにおける「反セム主義」の起源はどこにあるのか? まず歴史的なヨーロッパ・キリスト教社会におけるユダヤ人差別がある。それが近代になって人種、すなわち「血の問題」にすり替えられた。この人種という概念は、ヨーロッパの植民地主義が発明したものであり、植民地主義の暴力を支える理論の要となった。
近代における反セム主義は、その歴史的淵源をヨーロッパ・キリスト教社会に持ち、さらにそれが近代ヨーロッパのグローバルな植民地主義が生み出した人種概念と結びついて誕生したものだ。その近代の反セム主義に対するリアクション(反応)としてシオニズム運動が生まれた。
このシオニズムを支援したのが大英帝国だ。そこには大英帝国の帝国主義的な利害があると同時に、大英帝国の反ユダヤ主義がある。なぜなら国内のユダヤ人がパレスチナに自分たちの国を持ち、外に出て行くことは反ユダヤ主義者たちにとって好都合だからだ。
そして1947年、国連がパレスチナを分割し、そこにヨーロッパで難民となっているユダヤ人問題を解決するためユダヤ国家を作ることを決議する。なぜ国連がパレスチナを分割し、そこにユダヤ人の国を作るのか。しかも、ヨーロッパのユダヤ人の国を。
たとえば、アルジェリアの独立にさいしても8年にわたる苛烈な独立戦争が起き、双方で集団虐殺が発生した。このときアルジェリアを二つに分割し、フランス人の国とアルジェリア人の国を作るという解決があり得ただろうか。なぜパレスチナに関してそのような解決策が国連で提示されたのかといえば、このとき分割を支持した者たちに反セム主義があったからだ。「この者たちはヨーロッパ人ではなく、もともとパレスチナにいた者たちだ」という認識である。
どう考えても今パレスチナで起きている問題は、徹頭徹尾ヨーロッパにその問題の起源がある。歴史的にはヨーロッパ・キリスト教社会の問題であり、近現代においてはグローバルに植民地主義を展開したヨーロッパの問題である。その植民地主義が人間を人種に分け、それに優劣をつけて差別を合理化するレイシズムを生み、それがパレスチナの植民地支配を生み、パレスチナにおけるユダヤ国家の建設を正当化した。
そして戦後、とりわけ1970年代以降、ユダヤ人の悲劇としてのホロコーストが特権化、例外化され、ひたすらパレスチナ人に犠牲を強いることによってその清算をすることでパレスチナ占領の固定化、永続化が進行していく。
日本においては、戦後依然として脱植民地化が完了していないどころか、植民地主義の暴力が振るわれ続けているということが批判されてきたが、ガザのジェノサイドに対するG7の対応を見ても、これらの国々が植民地主義のカルテルであるということを今回のガザのジェノサイドは明らかにしている。
西洋とは、一方で普遍的人権や民主主義を掲げながら、一方で世界を植民地支配し、今なおその構造に立脚した差別、収奪の暴力を行使している、その矛盾を矛盾とも感じずにきたこと、それ自体がレイシズムの所産であると思う。
「アウシュヴィッツの後に詩を書くことは野蛮である」とのアドルノ(ドイツ哲学者)の言葉は、アウシュヴィッツの後に詩を書くことが野蛮であるか否かという枠でしか思考されてこなかった。だが問うべきは、アウシュヴィッツの前はどうなのか? ということだ。それをアドルノも問うていないし、アドルノの言葉に接してきた者たちも問わないできた。
近代の学知の中に、このレイシズムが内包されているのではないか。ガザのジェノサイドが日本の人文学研究者にとって他人事であるとしたら、それはこのレイシズムゆえではないのか。歴史的、今日的植民地主義の暴力を「他人事」としているからではないのかと思わざるを得ない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
岡真理(おか・まり) 早稲田大学文学学術院教授、京都大学名誉教授。1960年生まれ。東京外国語大学アラビア語科卒、同大学大学院修士課程修了。エジプト・カイロ大学留学、在モロッコ日本国大使館専門調査員、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を経て現職。専門は現代アラブ文学、パレスチナ問題。著書に『棗椰子の木陰で』(青土社)、『アラブ、祈りとしての文学』、『ガザに地下鉄が走る日』(以上、みすず書房)、『ガザとは何か』(大和書房)、共訳書にエドワード・サイード『イスラム報道』(みすず書房)、サラ・ロイ『ホロコーストからガザへ』(青土社)など。





















