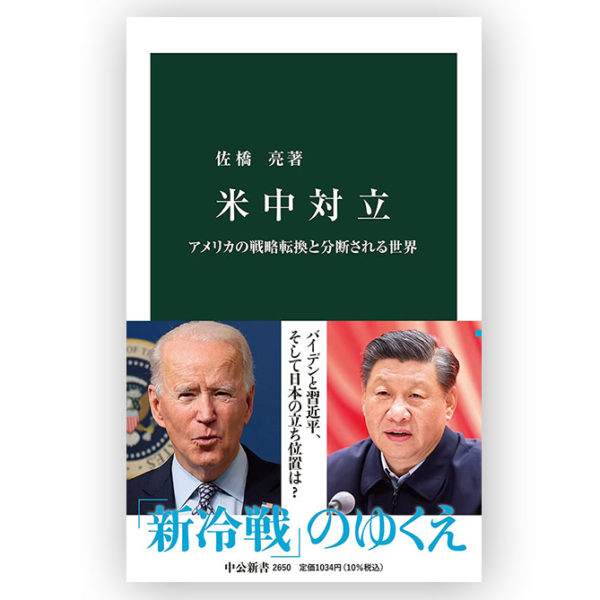 昨年は、米中国交樹立につながる大統領補佐官キッシンジャーの極秘訪中から50年目に当たる年だった。現在アメリカは、世界で影響力を強める中国に対して貿易や交流を絞り、人権侵害に対して経済制裁をおこない、ファーウェイ社製の次世代通信網(5G)関連設備を採用しないよう各国に圧力をかけている。大統領トランプが強めたこの対決姿勢をバイデンは継承し、むしろ加速させている。中国もアメリカとの関係を見直し、対米依存解消に動いている。台湾海峡周辺では、米中の軍隊が活動を活発化させている。
昨年は、米中国交樹立につながる大統領補佐官キッシンジャーの極秘訪中から50年目に当たる年だった。現在アメリカは、世界で影響力を強める中国に対して貿易や交流を絞り、人権侵害に対して経済制裁をおこない、ファーウェイ社製の次世代通信網(5G)関連設備を採用しないよう各国に圧力をかけている。大統領トランプが強めたこの対決姿勢をバイデンは継承し、むしろ加速させている。中国もアメリカとの関係を見直し、対米依存解消に動いている。台湾海峡周辺では、米中の軍隊が活動を活発化させている。
本書は東京大学東洋文化研究所准教授の著者が、半世紀前にアメリカがなぜ中国との関係を持とうとし、そしてそれをなぜ今転換しているのかについて、主にアメリカの学界の論考や新聞記事を参考にしつつ論じたものである。
著者はまず、「中国を育てたのはほかならぬアメリカだ。1972年のニクソン訪中、79年の米中国交樹立をへて、アメリカは40年以上にわたって中国に大規模な支援を与えてきた。中国人の多くの科学者の卵がアメリカの大学や研究所で学んだし、アメリカは中国に兵器や最先端の実験設備を売却し、中国に膨大な投資をおこなった。中国はグローバル化の申し子として世界の工場、市場になった」とのべている。
労働力と巨大市場求め 中国を育てたのはアメリカ
ニクソン訪中の前夜、アメリカは金ドル交換停止に追い込まれ、またベトナム戦争で敗北を喫して、経済は疲弊し政治的権威は失墜していた。このときニクソンは、社会主義の資本主義への平和的転化を狙って緊張緩和政策をうち出し、中国はソ連の脅威におびえる民族主義からこれに乗って親米路線に転換した。
1989年の天安門事件はアメリカによる政権転覆の政治の延長であり、天安門事件後も関与と支援政策は続けられた。その原動力になったのはアメリカの産業界であり、大学やシンクタンクに籍を置く御用学者たちだった。
中国の安価な労働力と巨大な市場を求めて、1990年代前半にアメリカの対中貿易と投資は急拡大した。製造業や農業、小売業だけでなく、中国でのインフラ整備や航空機購入などが商機と見なされ、「商機を他国に奪われるな」「対中貿易が国内雇用に直結する」との主張が広がった。アメリカ産業界の後押しで、中国への恒久的な最恵国待遇が実現し、中国はWTOに加盟した。
もう一つは、アメリカへの留学に門戸を開いたことだ。そしてアメリカで育った中国人科学者の大半(博士号取得者は9割)はそのままアメリカに残った。アメリカの新卒STEM(科学、技術、工学、数学)人材は年間約72万人で、その3分の1が外国人。アメリカのAI(人工知能)研究機関の人材の3割が中国人だ。シリコンバレーなど西海岸に本拠地を置くIT企業にとって、中国やインド出身の技術者たちは中核的な戦力になっているという。
一方中国は、欧米社会を利用する形で、先端技術を留学や企業買収を通じて自国に環流させた。また、政府金融機関から優先的に資金を調達した中国国有企業が成長していった。著者はこれを「国家資本主義の高まり」と評価している。そして「一帯一路」の独自の経済圏を世界に広げている。
ここで中国経済のしくみについては詳しくのべられていない。ただ、京都産業大学教授の玉木俊明氏の研究によると、1980年代からの新自由主義で、2010年代後半にはアメリカで上位1%の富裕層が社会の富の40%近くを所有するまでになったが、「社会主義」を標榜する中国も上位1%が同じく30%の富を所有する超格差社会になっている。そして監視技術も使った、国民に対する支配・抑圧がおこなわれている。
問題はアメリカの中国に対する関与政策がいつ転換したかだが、著者はその転換をリーマンショック後の2010年代と見ている。一方でリーマンショックで急速に力を低下させるアメリカと、対照的に国家資本主義の力で台頭する中国。中国がアメリカと世界経済を飲み込む未来への恐怖が、米産業界や学界の考え方を転向させたのだ、と。とくに科学技術の覇権争いで負けることがあれば、それは経済への影響にとどまらず、米軍の能力も危うくする。要するにそれは、資本主義の不均等発展のもとで生まれた、没落する古い帝国と、台頭する新たな帝国との対立にすぎない。
本書のなかで目を引くのは、この米中対立に対する各国の見方である。それは日本のメディアがほとんど報道しないものだ。
ヨーロッパ諸国は、確かに最近、軸足を中国警戒論に移している。しかし欧州全体で見たとき、中国はアメリカに次ぐ第二の貿易相手国であり、投資もEUから中国に1400億ユーロ、中国からEUは1200億ユーロに達した(2019年)。とくにドイツの対中輸出額はフランスとイタリアを足した額の3倍にのぼり、中国と投資協定も妥結した。だからアメリカの対中貿易への圧力に対しては反発があり、自律性を持った外交戦略を持とうとしている。英独仏はインド太平洋に軍事的プレゼンスを示すよう動いているが、台湾有事にどう反応するかについて一致はない。
クアッド(日米豪印戦略対話)の一角をなすオーストラリアやインドにしてもそうだ。鉄鉱石や石炭の対中輸出が重要なウエイトを占めるオーストラリアは、米中対立が国際秩序の基調になることを望んでいない。また「戦略的自律性」を重視するインドも、アメリカの戦略に乗って対中封じ込めの同盟を形成することには否定的だ。
シンガポールの元外務次官は、「独立した存在として行動する能力を失うことになる二者択一の世界観でなく、各国が異なったビジョンを提示する多元的な秩序がアジアにふさわしい」と提案している。ASEAN諸国の外交姿勢は、競合する大国のどちらにも与しないというものだ。
そうしたなかで日本が、アメリカの戦略に盲目的にしたがって対中国の鉄砲玉となることは、第一の貿易相手国を失い国益を損なうばかりか、日本列島を火の海にし国民の生命を危険にさらす愚かな選択にほかならない。それは唯一の被爆国としての世界からの信頼をも裏切ることになる。
(中公新書、302ページ、定価940円+税)





















