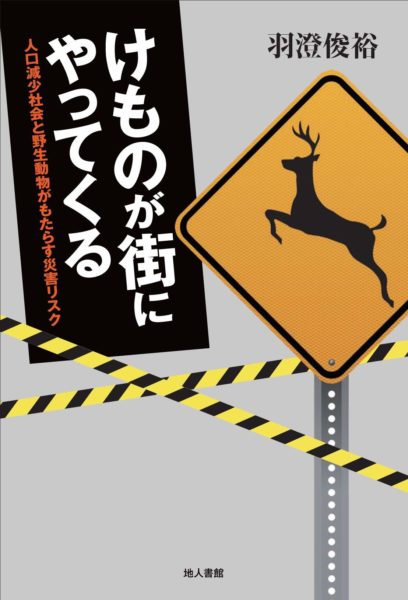
著者は東京農工大卒業後、環境省でツキノワグマ班研究員となり、その後野生動物保護管理事務所を立ち上げた。1970年代後半から40年以上も野生動物の仕事に携わり、各地の山に出入りしてきた経験から、最近よくニュースになるクマやイノシシ、シカなどの獣害の原因と解決方法について、一般の人にもわかりやすく提起している。
戦後復興から経済成長の時代、野生動物は「絶滅に瀕している」として保護の対象となっていた。だが、人口減少、少子高齢化が問題になってきたここ30年、野生動物が人間の生活圏に頻繁に出入りし、鳥獣被害がもたらされるようになった。
野生鳥獣による全国の農作物被害額は158億円(2018年)で、全体の7割がシカ、イノシシ、サルだ。同年の森林被害の面積は全国で約6000㌶で、その4分の3がシカによるものだ。それだけでなく都市部にも侵入して、人身事故や交通障害、感染症などのリスクをもたらしている。昨年度はクマによる人身被害が多くの都道府県で過去最高となった(全国では140件)。
なぜそうなったのか?著者は、それはあくまで人間の側の変化によるもので、野生動物はその変化に素直に反応しているにすぎない、という。
原因の第一は林業の衰退だ。日本の林業は、急峻な地形に苗を植え、間伐、下草刈り、枝打ちなど丁寧に手入れしながら育て、伐採し、山から下ろして製材するという、50~100年をスパンとする仕事をくり返してきた。ところが1960年代、政府は安い外材輸入に舵を切り、国内林業は衰退し、技術継承は絶たれてきた。
同時に、高度成長期には全国の奥山に水力発電用の大規模なダム建設が推進され、各地で土木的思考による破壊的な森林開発が進んだ。山麓の集落の水の枯渇を予防したり土砂災害を予防するなど、治山治水を重視した伝統的な林業の思想は顧みられなくなった。こうした奥山の大規模な土木的改変が、野生動物のすみかの森を攪乱した。東北地方のブナ林の乱伐を進めた結果、クマの出没が増えたと、マタギ猟師たちが怒っているという。
次に、農業と狩猟の衰退だ。かつて中山間地で生活していた百姓は、農業も林業も狩猟も、また土地の開墾、水の管理、草木の管理もすべて網羅しながら生活を維持していた。それがまた、人と野生動物との間の目に見えないバリアとなってきた。
ところが戦後、労働力は都会に出て行き、外国の農産物の輸入で農業自体が成り立たなくなった。今では高齢化した農家の耕作放棄地が荒れ地と化し、野生動物のすみかとなっている。1970年代に50万人いた狩猟免許所持者は20万人までに減り、獲物を山の恵みとしてあますところなく継続的に利用する狩猟文化は風前の灯火となっている。
もう一つは山の専門家が消えていることだ。従来、全国各地にある林業試験場(現在は国立研究開発法人森林研究・整備機構)が野生動物の基礎研究をおこない、林業の獣害対策を支えてきた。ところが、財源不足を理由に縮小、統廃合の対象になり、専門的な研究者は不在か、期間限定の非常勤雇用となっている。大学における野外の自然を探求する分野の研究室も同じだという。
獣害対策をしようと思えば、目撃、被害、捕獲情報を集中して分布の外周をつかみ、その頻度から生息密度の濃淡を読みとらねばならない。被害が出る場所には出てきてほしくないが、出没を防ぐには、生態学的な知見、行動学的な知見の蓄積が必要だ。その他、いつ発情期を迎え、いつ出産し、何頭の子どもを産むのか、何歳ぐらいまで生きるのかをつかみ、そこからどのくらいの捕獲までなら健全な集団として生き残れるか、対策の目安が見えてくるという。だが、森林が国土の7割を占める日本で、こうした森林管理の技術者も研究者も枯渇している。
アメリカに従属し経済効率一本槍で政治を進めてきた結果、将来にわたる国土の保全も困難になるような異常事態となっている。
では、獣害をどのようにして解決するのか。
著者によれば、必要なのは農作業を営む高齢者に寄り添う、若者の手助けだという。ときどき訪ねていっては、話し相手になりながら、ついでにサルを追い払ったり、畑の柵の張り具合を確認したり、必要なら補修もする。つまり過疎の進む集落の捨て置かれた状況を改善し、地域コミュニティを復活させることだ、と。
本書の中では、島根県の中山間地域センターの例が紹介されている。そこでは急速な人口増でなく「年に1%の定住者増」を掲げている。そして「大規模」「集中」「専門化」「遠隔化」が基本のこれまでの社会のしくみを、「小規模」「分散」「複合化」「近隣循環」という循環型社会に切り替えることを目標にしている。
そのめざすあり方は、自分の専門分野の仕事を核にしながら、農業をやり、治山治水のこともやり、観光客の相手もしながら、片方で介護の必要な高齢者を車で送迎し、日常の買い物のサポートもする。藪の刈り払い、ワナの見回り、銃による捕獲、捕獲した獲物の食品化、対象地域の動物調査などの仕事もある。こうした「生業の足し算」とでもいうべき働き方によって、新規定住者は必要な収入を得るし、地域の農林水産業の活性化もできる、というものだ。そのために仲間を募って組織をつくり、コミュニティの要望に応えることから始めてもよい、と。
それはコロナ禍を経験したわれわれへの、新しい生き方、新しい社会のあり方の提案といえる。
(地人書簡発行、四六判・234ページ、定価2000円+税)





















