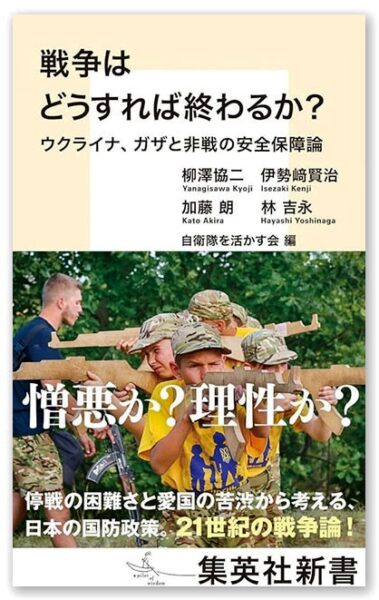
本書は「ウクライナ、ガザと非戦の安全保障論」の副題にみるように、今世界に衝撃を走らせている二つの戦争に対して、「非戦」「避戦」「停戦」の立場から具体策を追究する専門家4氏の論考と討論を収めたものである。ウクライナ戦争の停戦をめぐる論議をまとめる予定だったが、その後ガザでの事態が起こったことで、論考を追加しての出版となった。
論者は国連要員として紛争地の武装解除の指揮、自衛隊高級幹部や防衛官僚、大学教員などの経歴を持つ。それぞれの現状評価や問題意識はさまざまだが、「プーチンをやっつけろ」「ハマスのテロが今日の事態を引き起こした」といって停戦を妨げる言説とは一線を画し、現実に分け入って戦争終結の方策を探るという立場で一致している。
戦争長期化が招く大量虐殺
論者たちが「一刻も早い停戦」をとなえるのは、戦争が長期化するほど大量破壊兵器使用の危機が迫り、大量虐殺を許すからであり、それを停止させなければならないという思いからだ。停戦に向けては、戦争をめぐる「正義」や「戦争犯罪」への感情的な主張を棚上げする必要がある。停戦とは戦闘の一時凍結であり、それを早く実現させなければ「正義」は宙に浮いたまま、「戦争犯罪」の証拠をも風化させることになるのだ。
論者の一人、伊勢﨑賢治氏はウクライナへのロシア侵攻直後から「即時停戦」を訴えてきたが、それはこの戦争が単なる局地紛争ではなく日本に直結するからだと強調している。ウクライナでの戦争を奇貨とする勢力がロシアと中国との軍事的な緊張を煽り一気に軍備増強と動員準備を進めるなかで、「緩衝国家」としての日本と東アジア一帯の「ウクライナ化」が現実のものとなるという危機感からである。
しかも、「日本のウクライナ化」は日本がコントロールできない構造で起きるという。朝鮮国連軍(在韓米軍)の必要から生まれた自衛隊の性格から、朝鮮有事には自衛隊は参戦しなくても日本は自動的に国際法上の正当な攻撃目標になるのだ。
伊勢﨑氏はここで、ウクライナ戦争にいたって「普段からの平和主義・護憲派が、日本共産党を中心に、アメリカが軍事協力する紛争の当事者の一方を賛美し、応援し始めたこと」、つまり「ロシアの絶対悪魔化への、みごとな翼賛化」を遂げたことに注意を向けている。改憲派と護憲派が一体となって「“即時停戦”派を攻撃する」という構図が生まれているという指摘である。
本書の論議から、ウクライナ戦争が「強行派」「リベラル派」を問わず吹聴するような、「いきなり平和を破壊したロシア」に対するウクライナ側の「専守防衛」といったものではなく、2014年からのドンバス内戦から続くアメリカ・NATOの代理戦争であることが浮かび上がってくる。それは今のガザでの事態を語るときに使われる「ハマスのテロも容認できない」という自己保身的な枕詞が、ハマスを生み出した歴史的経緯を覆い隠し、民主的選挙で生まれた政体(=交渉相手)を否定する方向で、「イスラエルによる民族浄化を止める停戦に向かわせない役割」を果たしているという指摘にもつながっている。
このように現実の戦争を歴史的論理的に見ようとせず、一局面の現象に悲憤慷慨して「敵を倒すまで戦う」という主張が、戦禍にさらされた罪のない人々にさらなる犠牲を強いることは明らかだ。麻生太郎元首相が台湾を訪れ、「台湾も日本もアメリカも戦うことを覚悟すべきだ」といった。その前に、北方領土をめぐって「ロシアとの戦争」を煽る国会議員もいた。さらに、そのような言動を非難し「武力行使による国際紛争の解決」を禁止した憲法九条の擁護を叫ぶ者が「ロシアの侵略と戦うウクライナと連帯する」と戦闘を煽るという転倒が起こっている。
無法軍事国家・日本の現実
その「戦争」や「覚悟」「連帯」が現実にどのような結果をもたらすのかについて深く考え想像したことのない、つまり戦争について彼我のありのままの現実を知らない政治家に委ねる「シビリアンコントロール」の危うさも論議になっている。さらに、憲法論議が実態から遊離して空洞化し、日本が法整備のうえからも戦争できない国になっているという現状についての論議も、現場の自衛隊員の苦悩など現場での実感をともなって説得力を持つ。
憲法上、武力紛争地に派遣できないため、PKO部隊の「駆けつけ警護」として南スーダンに派遣された陸上自衛隊が、宿営地周辺で迫撃砲を使った「激しい戦闘」に直面した。そのとき、ルールが異なる他国の軍隊と同じ対応がとれず厳しい状況に置かれた。その日報で「戦闘」と記していたにもかかわらず、政府は「法的には衝突」(当時・稲田防衛相)といって恥じなかった。自衛隊はそのような政治家のコントロール下にあるのが現実だ。
また、あまりつまびらかにされない重要なこととして、「戦争犯罪」という概念が刑法にも自衛隊法にもないことが論議に上っている。この問題は、自衛隊は軍隊ではなく、戦争犯罪を犯すことを考えなくていい(考えてはならない)というスタンスに起因するものだった。にもかかわらず軍備は拡張の一途をたどり、自衛隊の海外派遣、米艦の防護や米軍指揮下の海兵隊化が進み、さらには「敵基地攻撃」まで叫ばれるまでになった。そのもとで、日本は今や「無法軍事国家」となっていることが暴露されている。
日本はジュネーブ条約(交戦法規)に加入しているが、それにもとづく国内法(交戦中の違反行為=戦争犯罪)の整備がなされていないことから、武器使用を命令した「上官責任」は問われない。指揮官と隊員はまさに「ヤクザの親分と鉄砲玉の子分」のような関係に置かれている。また「国外犯規定」もないことから、海外で犯す業務上過失も法的な処罰ができない状態にある。
こうした状況は、アメリカの戦略に合わせた成り行きまかせの戦後の防衛政策の帰結であること、だからこそ、中国やロシア、北朝鮮との対話をそれ以上に重視し平和を確保することの意義も浮き彫りにされている。そのうえで、柳澤協二氏(元防衛官僚)の「日本の官僚は、アメリカとの関係でしか世界を見ていないし、アジアのことを知らないと言われれば、その通りだ」という言葉が印象に残った。
(自衛隊を活かす会編、集英社新書、250㌻、960円+税)






















文字読みが苦手な方はこちらの当日の動画配信をご覧ください
https://www.youtube.com/watch?v=Jy4-vvIINsI